突然の入院から退院が近づいてくると、「このまま家で介護できるのだろうか…」
「家族も仕事があるのに、在宅は難しいのでは?」そんな不安を抱えるご家族は少なくありません。
私自身、看護師として30年以上病院に勤め、数多くの患者さんやご家族の声を聞いてきました。
「命は助かったけれど、以前の生活に戻るのは難しい」そんな現実に直面することもあります。
では、その時どうすればよいのでしょうか。

選択肢のひとつとして「施設」という道を知っておくことは、とても大切です。
この記事では、介護施設の種類や特徴、選ぶ際のポイントをわかりやすく解説します。
さらに、私が現場で関わった患者さんの実例もご紹介。
医療と介護の両方の現場を見てきた立場から、安心につながる情報をお届けします。
施設選びに迷っている方に役立つ内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。
介護施設の種類と特徴
 さくら
さくらここでは、代表的な8種類の介護施設を一覧表にまとめました。
対象となる介護度や特徴を整理していますので、施設選びの参考にしてください。
ここでは、代表的な8種類の介護施設を一覧表にまとめました。
対象となる介護度や特徴を整理していますので、施設選びの参考にしてください。
| 施設の種類 | 区分(公的/民間) | 対象となる介護度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 介護付き有料老人ホーム | 民間 | 自立〜要介護5 ※施設によって異なる | 介護サービスが付いた民間施設。入居金や月額費用に幅がある。常時介護が必要になった時にも安心できるが、サービス内容は施設ごとに差が大きい。 |
| 住宅型有料老人ホーム | 民間 | 自立~要介護5 ※施設によって異なる | 生活支援が中心の民間施設。介護が必要になった場合は外部の訪問介護サービスなどを利用。自由度が高く、自立して生活したい人に向いている |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 民間 | 自立~要介護5 | バリアフリー設計の住まいで、安否確認や生活相談などの見守りサービスが付く。介護が必要になった場合は外部の介護サービスを利用。自由度が高く、比較的元気な高齢者に向いている。 |
| グループホーム | 民間(地域密着型) | 要支援2〜要介護5(認知症) | 認知症の高齢者が少人数で共同生活する施設。家庭的な雰囲気の中で介護や見守りを受けられる。地域とのつながりを大切にしており、安心感のある暮らしができる。 |
| ケアハウス | 公的 | 自立~軽度の要介護 | 高齢者向けの住宅型施設で、食事や生活支援サービスを提供。比較的費用が安く、自立して生活できる人が対象。将来介護が必要になった場合は外部の介護サービスを利用。 |
| 特別養護老人ホーム(特養) | 公的 | 要介護3以上 | 公的施設で費用が比較的安い。生活の場として長期入居が可能。医療ケアは限定的で、入居までに待機が長くなる場合が多い。 |
| 介護老人保健施設(老健) | 公的 | 要介護1〜5 | 退院後の在宅復帰を目指す施設。リハビリや医療ケアを受けながら生活できるが、入居は原則3か月〜6ヶ月など短期間。医師や看護師、リハビリスタッフが配置されている。 |
| 介護医療院 | 公的 | 要介護1〜5 Ⅰ型:医療依存度が高い人 Ⅱ型:比較的安定している人 | 長期的に医療と介護の両方が必要な人のための施設。医師や看護師が常駐し、医療ケアを受けながら生活できる。ターミナルケアにも対応。 |
それぞれの介護施設には役割や特徴があり、「どれが正解か」ではなく、「その方の状態や家族の状況に合っているか」で考えることが大切です。
要介護度だけでなく、医療的なケアの必要性や、今後の生活の見通しによっても選択肢は変わります。
迷ったときは、地域包括支援センターやケアマネジャーなど、第三者の専門職に相談しながら整理していくと安心です。
失敗しない施設選びのポイント



施設選びで後悔しないためには、見学が欠かせません。
パンフレットやウェブサイトだけでは十分な情報が得られません。
実際に見学に行くことで、その場の雰囲気やサービスの詳細が明確になるため、可能であれば親御さんと一緒に施設見学に行きましょう。
施設見学のポイント:事前準備
- 親の意向を確認する:ご両親が望むサービス、レクリエーションがあるか。
- 質問事項をメモする:見学時間は限られているため、あらかじめ質問内容を考えておく。
- 複数施設を候補にする:複数の施設を見学し、比較検討するとよいため、2〜3ヶ所施設を探しておく。
施設見学:当日見るべき3つのポイント
いよいよ見学当日。全部を完璧にチェックする必要はありません。
まずは 次の3つだけは必ず確認しておきましょう。
- 入居者の表情:穏やかで生き生きとした表情で過ごしているか
- スタッフの対応:笑顔で丁寧に接しているか、言葉づかいはどうか
- 施設の清潔感:全体が清潔に保たれ、生活感が感じられるか
看護師の立場から見ても、この3つは特に重要です。
これはパンフレットやホームページでは分からない、「現場の雰囲気」がここで一番よく伝わるからです。
実際に足を運び、自分の目で確かめることが大切です。
入居者が集まるお昼時に見学できると、現場での雰囲気がわかりやすく、おすすめです。
さらにチェックできると安心なポイント



時間に余裕があれば、以下の6つの観点で見てみましょう。
入居者の表情と様子
- スタッフとの間で温かいコミュニケーションが取れているか
- 身だしなみや髪型が整えられているか
スタッフの関わり
- 職員同士の雰囲気は良いか
- 質問に対して丁寧に説明してくれるか
建物や設備のハード面
- 日当たりやバリアフリー設備はどうか
- 車椅子で移動しやすいか
- プライバシーは確保されているか
- 個浴・大浴場・機械浴(特殊浴)など、個々の状態に合わせた設備があるか
介護や医療体制
- スタッフ数や夜間体制は十分か
- 認知症ケアや医療対応の仕組みはあるか
- 緊急時の対応はどうか
食事や生活の様子
- メニューの工夫や、刻み食・ミキサー食などの対応は可能か
- レクリエーションやリハビリテーションが充実しているか
- 本人の興味や趣味に合わせた活動はあるのか
- 日々の生活にメリハリがあるのか
費用と契約内容
- 入居一時金・月額利用料の内訳を明確にしているか
- 別途発生する費用(オムツ代・医療費など)の説明があるか
- 退去条件の確認(病状が悪化した場合など)はどうか
病院での事例
私が出会った50代のAさんは、まさに「退院後どうするか」という課題に直面していました。
Aさんはご自身が病気の治療のために入院することになり、長年在宅で介護してきたお母様の今後を考えざるを得なくなったのです。
Aさんのお母様は、要介護4でほぼ寝たきり状態。
ご病気であるAさんが、24時間体制で介護をされていました。
「大切なお母様を自宅で介護したい。」という強い思いで長年介護されていました。
今回、ご自身の体調が思わしくなく担当ケアマネジャーさんとご相談の上、施設入所を決断されました。
面談中に、「十分、母の介護をしてきました。施設入所が決まり、肩の荷が降りました。」
「これからは、自分の病気の治療に専念します。」「退院したら、母に会いにいきます。」とお話してくださいました。
施設入所を決断するまで、色んな葛藤があったと思います。
大切な親御さんを施設に入れることに「罪悪感」を感じると話される方も見えますが、介護はプロに任せて、ご自身の心や体を大事にすることも大切です。
この記事を読んでいるあなたも、同じ不安を抱えているかもしれません。
そんな時に「施設という選択肢」を知っておくことは力になります。
この記事を参考にしていただけると幸いです。


今日のまとめ
退院後の生活を考えるうえで、「施設」という選択肢を知っておくことはとても大切です。
在宅介護だけで抱え込もうとすると、家族の負担が大きくなり、心身ともに疲れてしまうことも少なくありません。
施設について事前に理解しておくことで、無理のない介護の形を選びやすくなります。
介護施設にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。
実際に検討する際は、可能であれば見学を行い、入居者の表情やスタッフの対応、施設内の清潔感などを確認することが、安心できる選択につながります。
そして何より、大切な親御さんを思う気持ちと同じくらい、ご自身の心と体を守ることも忘れないでください。
この記事が、ご家族にとって納得のいく施設選びを考えるための一助となれば幸いです。
入院がきっかけで施設を検討するケースも多くあります。
実際に「親が突然入院!」となった時に慌てないよう、こちらの記事も参考にしてくださいね。
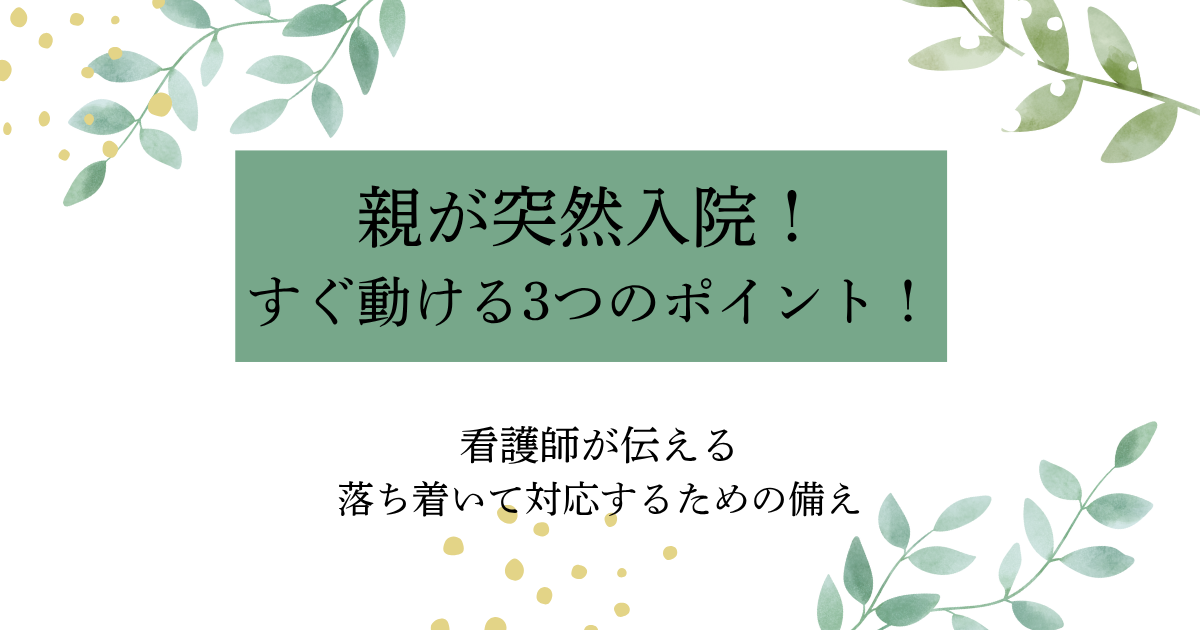
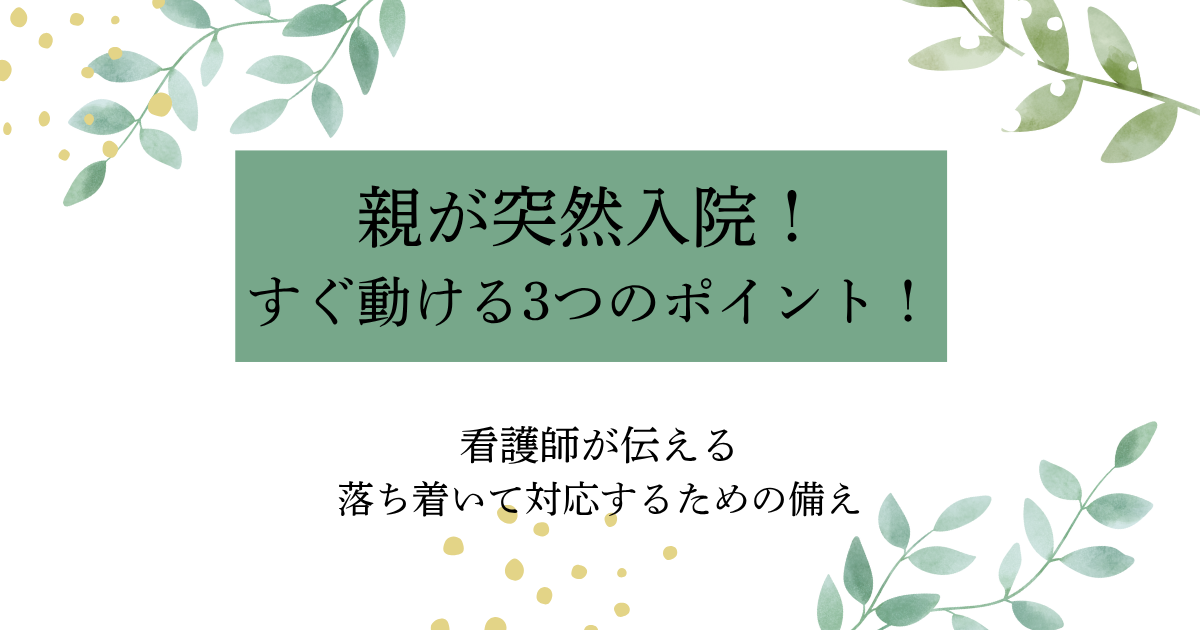
次回予告
「施設という選択肢」を考えることは、退院後の安心につながります。
でも、いざ入所を決めるとなると『本当にこれでいいのかな…』と罪悪感を抱く方も少なくありません。
次回は、親を施設に預けるときに多くのご家族が感じる「罪悪感」と、どう向き合えばよいのかを一緒に考えていきます。

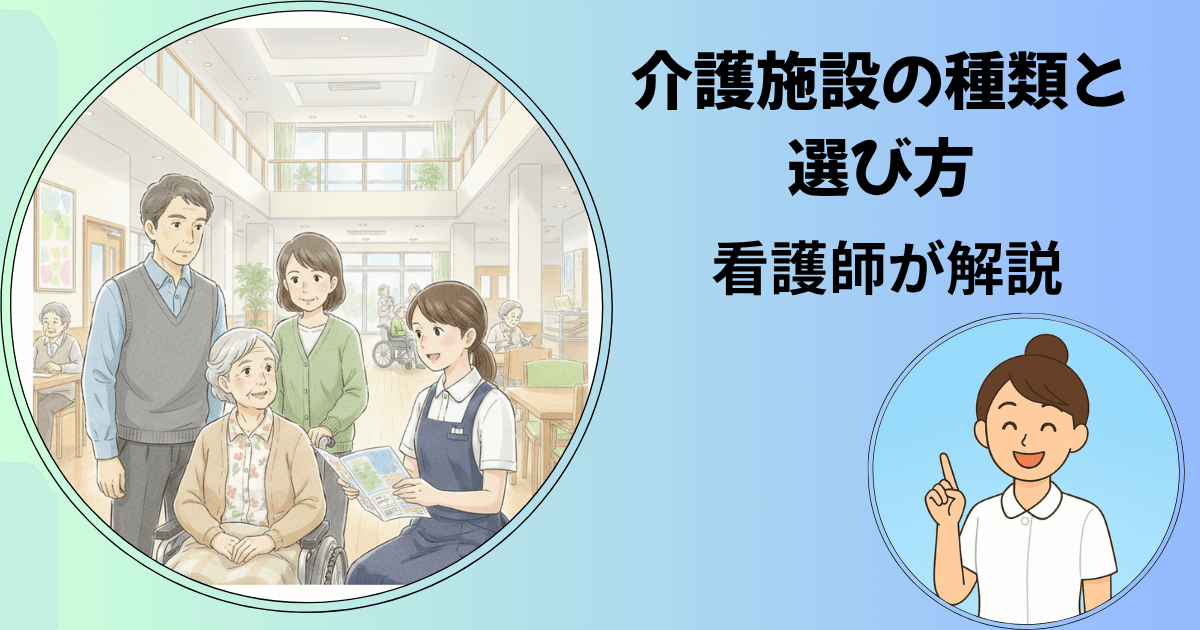
コメント