こんにちは。看護師として30年以上、医療と介護の現場に関わってきたさくらです。
親の老いと向き合いながら、50代の今を大切に暮らしています。
このブログでは、看護師としての経験から日々寄せられるご家族の相談や、同じ立場の方に役立つ情報を、わかりやすくお届けしています。
今回は、介護保険の「申請から、サービス開始までの流れ」についてお話します。
前回は介護保険の基本をまとめましたが、実際には「どんな書類が必要?」「申請はどこで?」「どのくらい時間がかかるの?」といった声が多く届きます。
私が現在勤務している「患者相談室」にも、退院前のタイミングで介護保険について不安を抱えたご家族がたくさん相談にいらっしゃいます。
制度は知っていても、「いつ・どこで・何をすればいいのか」が分からないと、次の一歩が踏み出せないものです。

そこで今回は、申請時に必要な書類・認定の流れ・よくある質問(認定期間や仮のサービス利用など)を、看護師の視点から具体的に解説していきます。
介護保険の仕組みをしっかり理解しておくことで、いざというときに困らず、安心して在宅生活への準備を進められるようになります。
どうぞ最後までお読みいただき、ご自身やご家族のために役立てていただけたら嬉しいです。
介護保険申請に必要な書類は?
※申請に必要な書類は、お住まいの地域や状況によって変わることがあります。くわしくは市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談してみてください。
 さくら
さくら「じゃあ実際に介護保険を申請するには、どんな書類が必要なのかな?
今日はそこを一緒に見ていきましょう。」
●65歳以上の方の場合
→ 申請書(介護保険要介護認定・要支援認定申請書)、介護保険被保険者証でOKです。
●40歳〜64歳の方の場合
→ 上の申請書に加えて、健康保険証(医療保険証)を一緒に出してください。
申請書のフォーマットは市区町村の窓口やホームページからダウンロードできます。
あわせて マイナンバーカードや運転免許証 も忘れずに持参しましょう。
申請書には「面接調査日程等の連絡先」を記入する欄があります。
さらに、かかりつけ医の情報(主治医の名前・病院名・電話番号など)も必要になります。
あらかじめ確認しておくとスムーズです。
また、家族で話し合って「当日、親御さんの状況をきちんと伝えられる人」が立ち会うと安心です。
介護保険サービス利用までの流れ



「ここからは、介護保険サービスを実際に利用するまでの流れを一緒にわかりやすく見ていきましょう。
初めての方でも大丈夫。順番にお伝えします!」
申請書を提出する
必要な書類をそろえたら、市区町村の窓口へ提出します。
「いきなり役所に行くのはちょっと不安…。」という方は、地域包括支援センター(包括) に相談してみるのがおすすめです。
申請の相談に乗ってくれたり、代わりに申請してくれる場合もあるのでとても心強い存在です。
認定調査と主治医意見書の作成
認定調査とは?
申請後、だいたい10日前後で「認定調査」が行われます。
市区町村の職員さんや、委託を受けたケアマネジャーさんが、ご本人のご自宅を訪問して、心身の状態や普段の生活の様子を確認します。
とても大事なステップなので、リラックスして臨んでくださいね。
たとえば質問される内容は、
- 歩くときにふらつきはないか
- 食事や着替えに介助が必要か
- 家族からどのくらいサポートを受けているか
などです。
ご本人だけで答えるのが大変なときは、家族も一緒に立ち会って大丈夫です。
また、調査のときに「親御さんの病歴や最近の体調変化をメモしておく」 ことも役立ちます。
▶詳しくは 親の介護が突然必要に!備えておくべきポイント!【第1話】
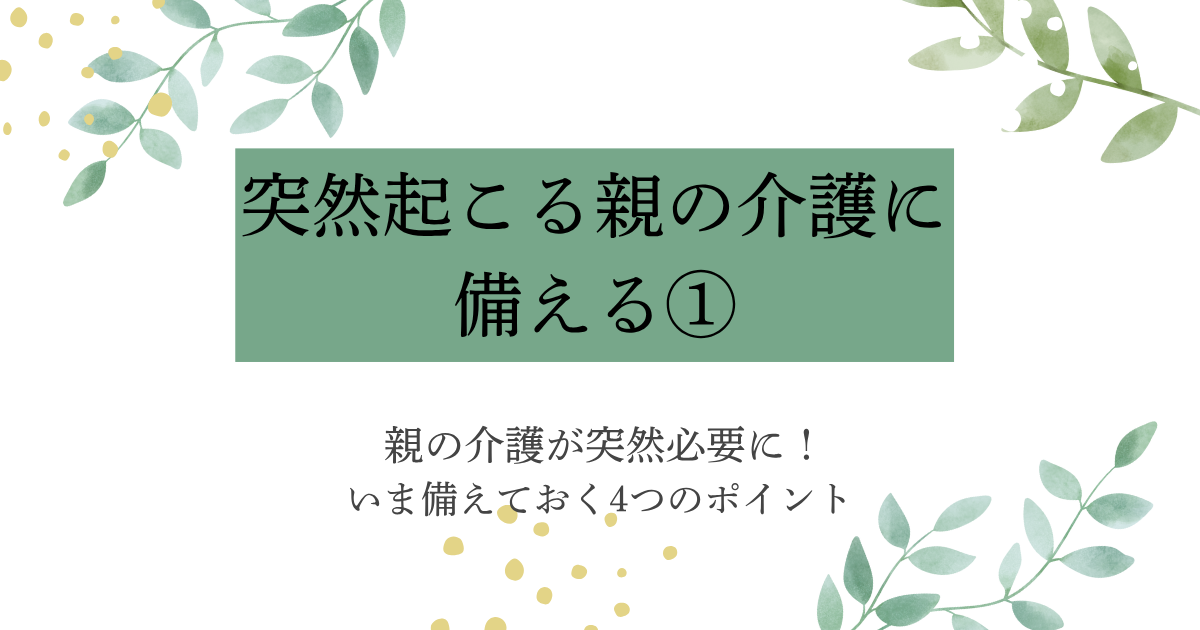
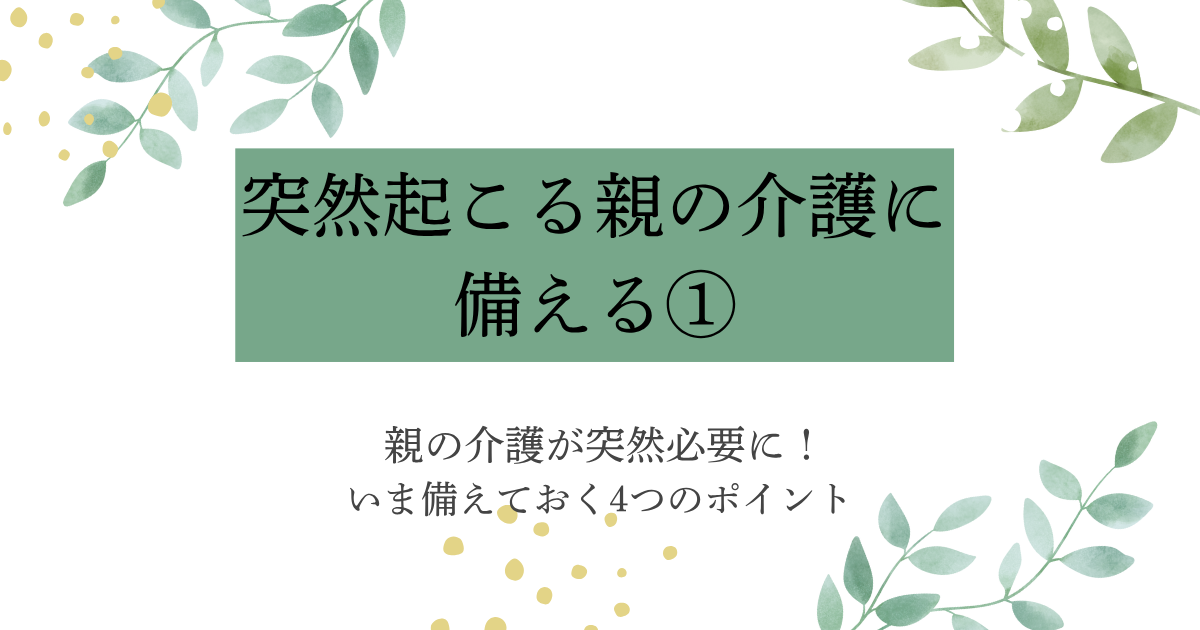
主治医意見書とは?
認定調査とあわせて、市区町村から申請書に記載した主治医へ「主治医意見書」の作成依頼 が届きます。
これは、申請者さんの心身の状態や持病などについて、主治医の視点からまとめてもらう大切な書類です。
もし申請のときに「かかりつけ医がいない」という場合でも、市区町村の窓口で相談できますので安心してくださいね。
なお、この 意見書の作成費用は市区町村が負担してくれるのでご本人の自己負担はかかりません。
審査判定 通知
一次判定と二次判定を経て認定結果の通知が申請から約30日。
認定結果通知書と要介護度が記載された新しい介護保険被保険者証が郵送されます。
急に病気やケガで介護が必要になったり、退院してすぐに介護サービスを利用したい場合など、「1ヶ月も待てない!」と感じることもあると思います。
そこで、この「結果待ち」の期間に、必要に応じて介護サービスを利用できるよう「暫定措置」があるため、安心してください。
認定区分(区分をわかりやすく)
自立:介護不要
要支援1・2:少しだけ手助けが必要
要介護1〜5:身体の状態によって、たくさんの手助けが必要
(数字が大きくなるほど、必要な介護量も多くなる)
ケアプラン(介護予防サービス計画書)ってなに?
認定された結果に合わせて、ケアマネジャーという専門家が、どんなサービスを使うか一緒に考えて計画を立ててくれる。
この計画のことを「ケアプラン」といいます。
例えば、「週に2回、ヘルパーさんに家事を手伝ってもらう」「デイサービスに行って、みんなと交流する」など、具体的なサービスを決めます。
前述した、「暫定措置」ケアプランについても、ケアマネジャーが作成してくれます。
ケアマネジャーは常にご家族に寄り添いながら、最善の提案をしてくれる存在です。
まるで「アンパンマン」や「スーパーマン」みたいに、頼りになるヒーローです!
良好な人間関係が築けるといいですね。
介護サービスの利用開始
いよいよ介護サービスの利用が始まりますね。
サービスを使うことで、ご本人もご家族も少しほっとできる時間が増えるはずです。
初回はケアマネジャーさんやスタッフさんが、利用内容やスケジュールを確認してくれます。
安心してスタートしましょう。
- 週に何回利用するか
- デイサービスに行く曜日
- 費用の説明
など、分からないことがあれば遠慮なく相談してくださいね。
介護サービスは「チームで支える」仕組みなので、気になることはどんどん伝えて大丈夫ですよ。
まとめ


親の介護が必要になったとき、「まず何から始めればいいの?」と戸惑う方も多いと思います。
でも、基本の流れを知っておくだけでも、ずいぶん気持ちが楽になります。
申請には書類の準備が必要ですが、わからないことは地域包括支援センターで相談に乗ってもらえます。
また、認定調査には、できるだけご本人のことをよく知るご家族が立ち会うと安心です。
申請から認定まではおおよそ30日。
ただし、急なケースでは「暫定措置」という制度もあるので、心配なときは遠慮なく相談してみてください。
ケアマネジャーさんは、介護の心強い味方。
家族に寄り添って、今後の生活を一緒に考えてくれる存在です。
良い関係を築いておくと、サービスが始まってからも安心です。
こうしたポイントをおさえておくことで、「知らなかった…。」と焦ることも減ります。
ぜひ、今のうちから少しずつ準備を始めてみてください。
さらに介護保険の基本的な仕組みについて知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
▶詳しくは 「親の介護が突然必要に!介護保険・前編」【第3話】
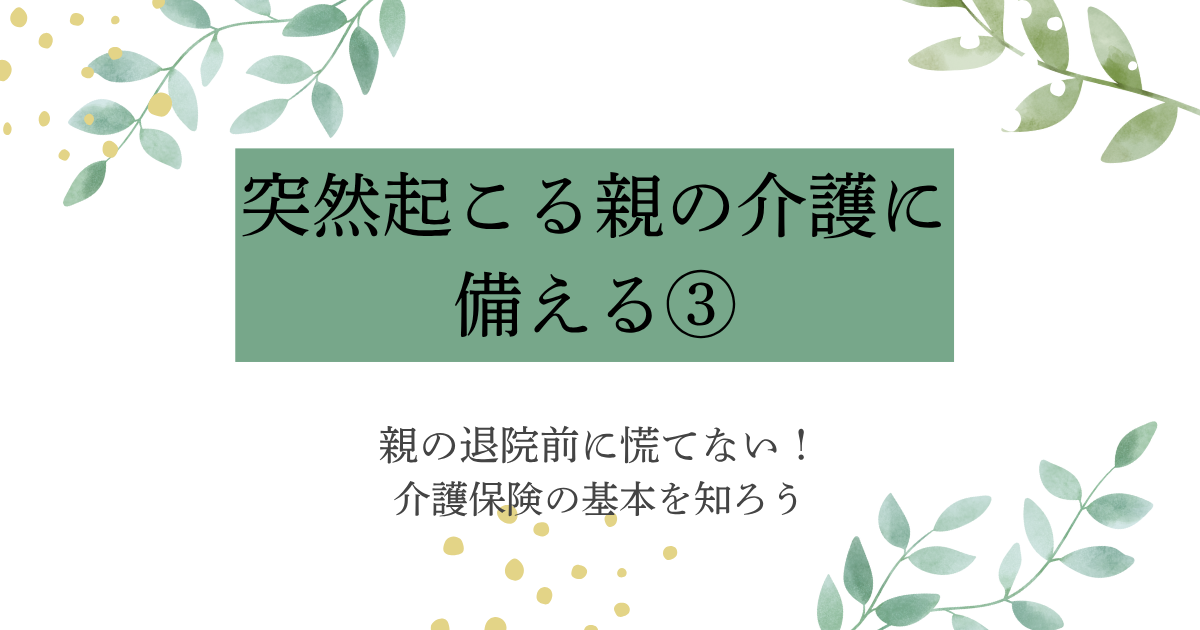
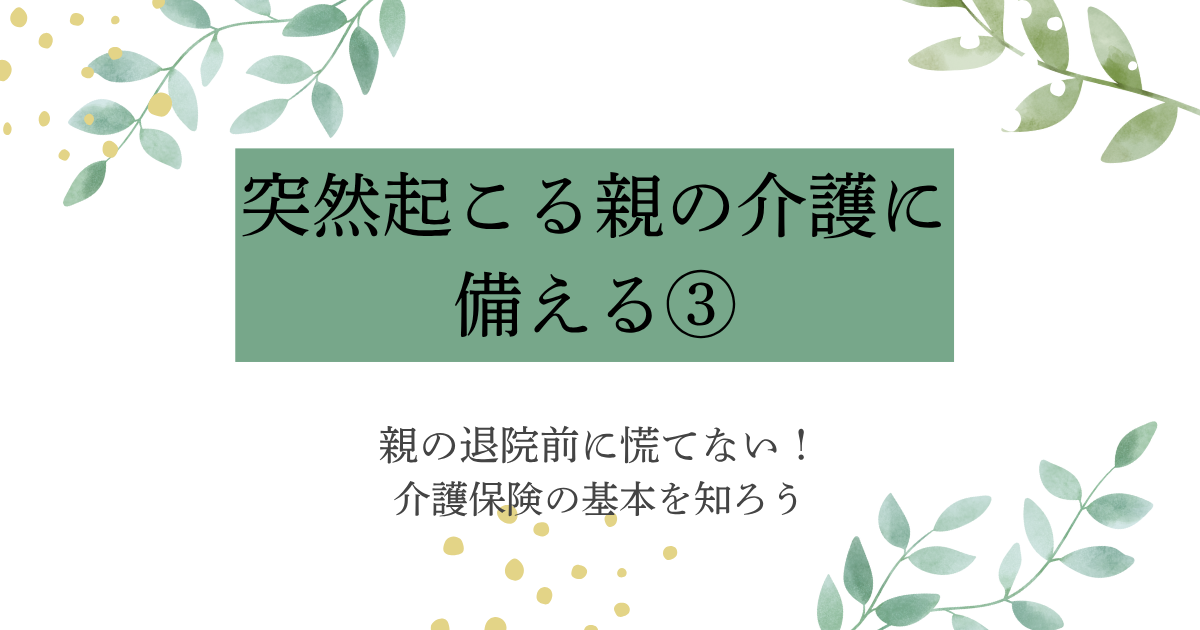
介護保険の申請やサービス利用の流れについては、厚生労働省の公式ページも参考になります。 ▶介護サービス利用までの流れ(厚生労働省)https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html
わが家の介護体験談
私には大正生まれの祖母がいて、母が忙しく働いていたこともあり、小さいころから祖母に育ててもらったと言っても過言ではないほど、いつも私のそばには祖母がいました。
孫の私にはとても優しい祖母でしたが、母との「嫁vs姑」問題は絶えることなく、家の中は常に不協和音が流れていました。
私は20歳の時には自立し、病院での寮生活が始まります。
両親と祖母の3人暮らしでしたが、両親は定年を機にして八ヶ岳の麓に移住、祖母は住み慣れた家を離れることができず、「ついて行かない」と決断します。
祖母が90歳前後のころ、認知機能が低下し徘徊するようになりご近所からクレームが入るようになりました。
近所に叔母が住んでおり、最初は「私が面倒を見る!」と頑張っていましたが、実の母親が老いていく姿を受け入れることができず、声を荒げることが増えていきました。
叔母も「もう無理」と介護疲れがマックスとなり、最終的には両親が信州で引き取ることになります。
引き取られた後も、父は叔母と同じように、老いていく母の姿が受け入れられず、叔母と同様に声を荒げることが多かったようです。
不思議なもので、冷静に介護ができたのは母でした。
あんなに口論が絶えなかった二人なのに…。
デイサービス、ショートステイ、等家族に負担がかからないようにとケアプランを立てていただきました。
両親のセカンドライフも守りつつ、在宅で祖母を看取ることができたのは、ケアマネジャーさん、訪問看護師さん等沢山の支援があったからですね。
また、母が最後まで祖母に寄り添い、頑張ってくれたからこそ、あの最期があったのだと思います。
今、現在介護に奮闘されている方、一人で抱え込まないように、介護サービスを受けながらご自身の体をいたわり、今日という一日を少しでも充実した日にしてください。
次回予告
●「ケアマネジャーの役割とは?」 失敗しない選び方・変更方法を看護師がわかりやすく解説、についてお伝えします。
介護に欠かせない存在「ケアマネジャーさん」について。
- どんな役割をしてくれるの?
- どうやって関わるの?
- 変更したいときはどうすればいい?
そんな疑問に、看護師目線でわかりやすくお伝えします。
また、ぜひ読みに来てくださいね。

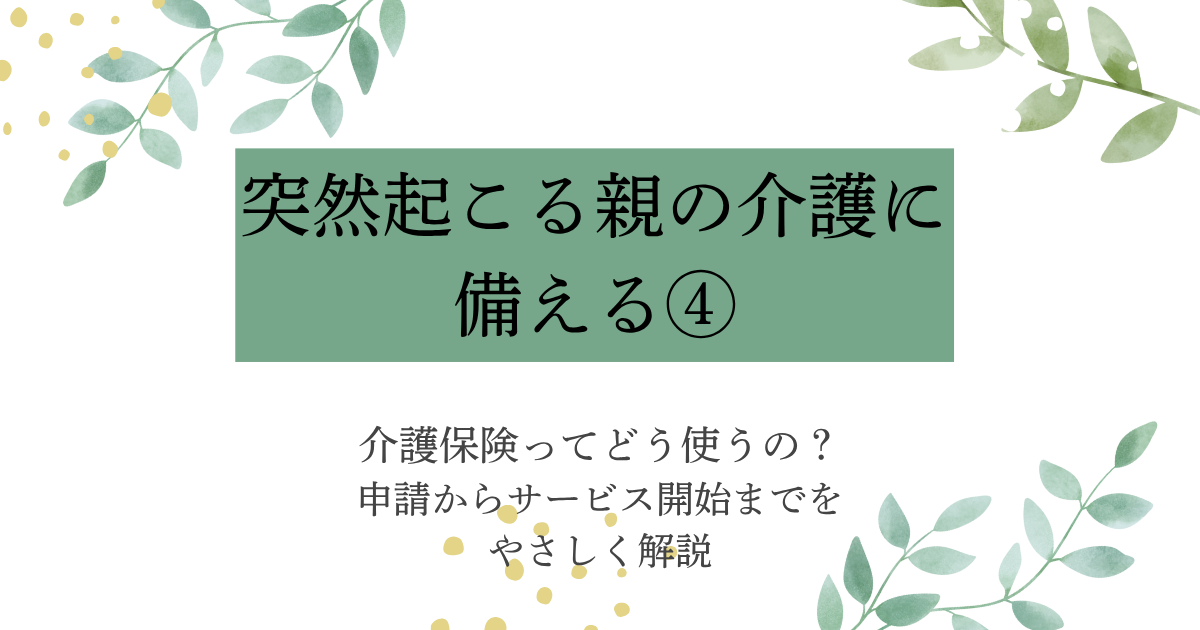
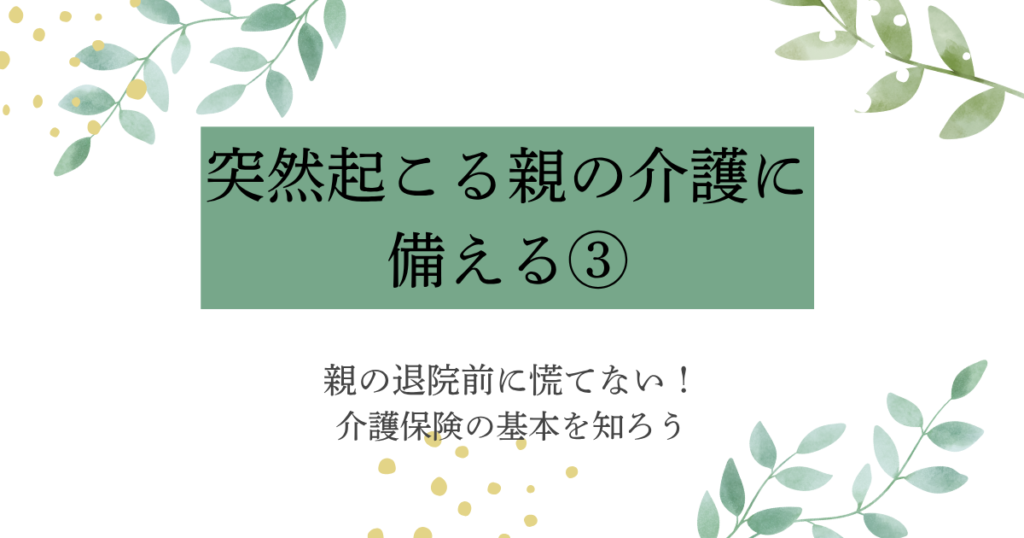
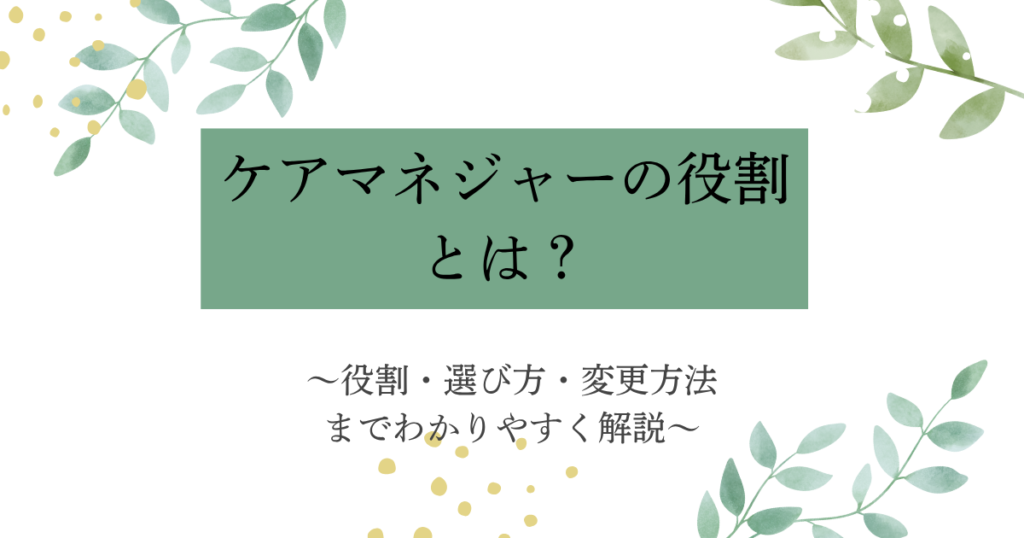
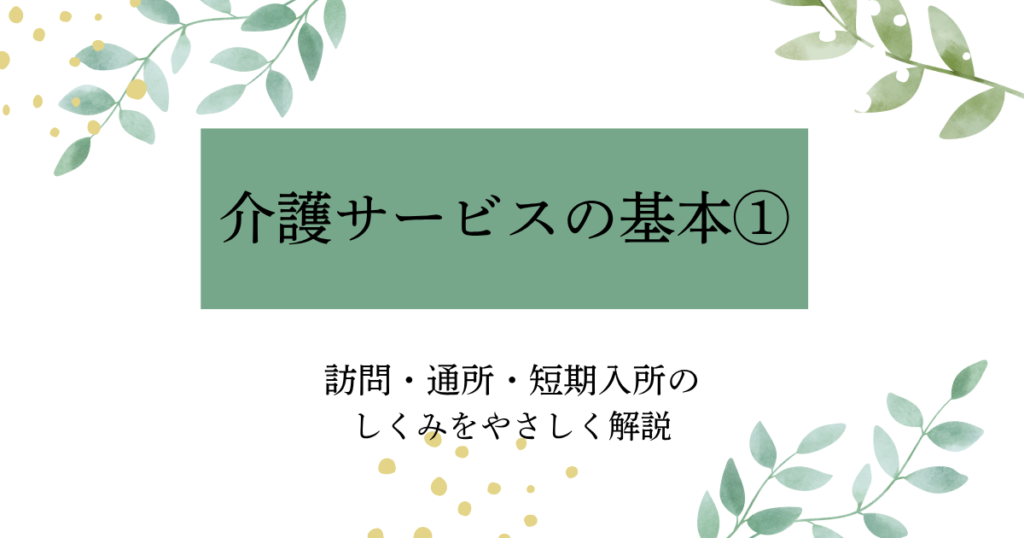
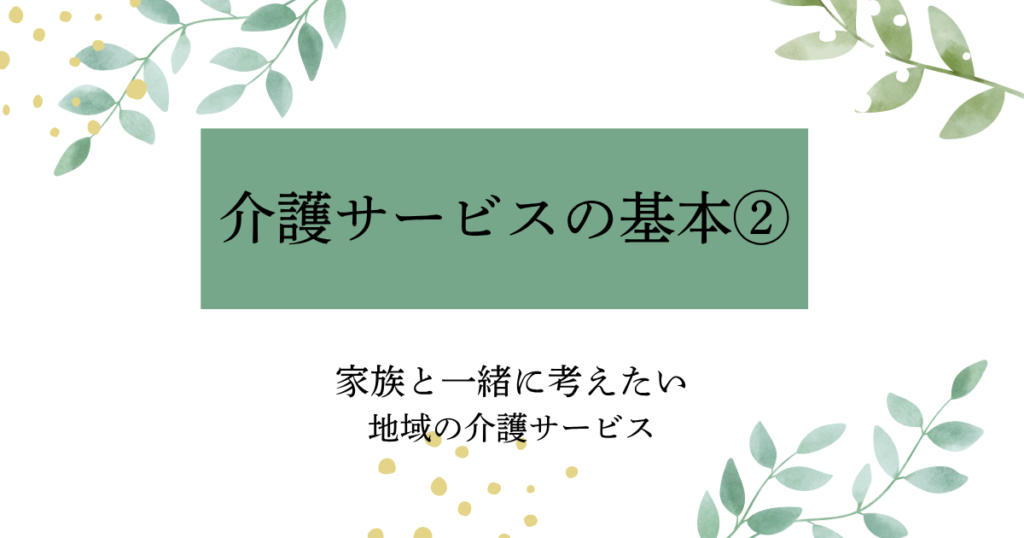
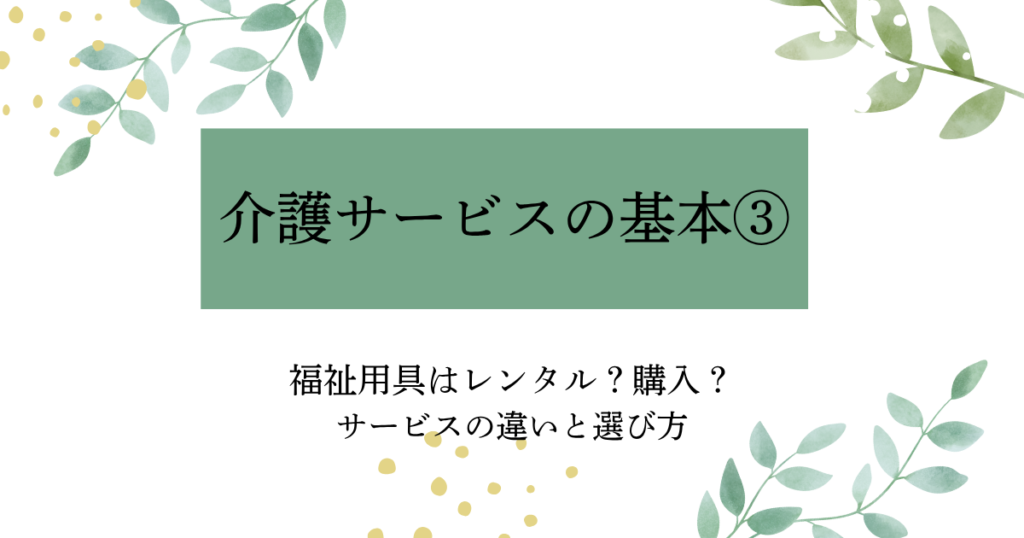
コメント