こんにちは。看護師として30年以上、医療と介護の現場に関わってきたさくらです。
離れて暮らす親御さんのことを思うと、「ちゃんとご飯を食べているかな?」「高齢になって買い物も大変そう」「栄養が偏っていないか心配」
そんなふうに、不安を感じることはありませんか。
実は、介護保険外でも利用できる自治体サービスを知っておくことで、こうした不安を解消できるケースも少なくありません。
自治体の宅配食や家事支援サービスを活用すれば、買い物や調理の負担が軽くなり、火元への不安も減ります。

私がこれまで関わってきた患者さんの中にも、こうしたサービスを上手に取り入れて、安心して暮らしている方が少なくありません。
この記事では、高齢の親御さんを支える自治体サービスについてわかりやすく解説します。
栄養サポートや家事の軽減になるので、ぜひサービスの内容を知っておいてください。
最後まで読んで、少しでも親御さんが安心して暮らせるきっかけにしていただけたら幸いです。
高齢者向けの自治体配食サービスとは?内容と利用のポイント
 さくら
さくら自治体の配食サービスとは、主に高齢者や食事の準備が難しい方に向けて、栄養バランスのとれた食事を自宅まで届けてくれるサービスです。
多くの自治体では、ただ食事を届けるだけでなく 安否確認 も兼ねており、利用者が安心して生活を続けられるように支援しています。
対象者や利用回数、料金、申し込み方法は自治体によって異なりますが、共通しているのは、「高齢者の健康維持や在宅生活のサポートに役立つ」という点です。
配食サービスの特徴



自治体の配食サービスには、次のような特徴があります。
- 高齢者や一人暮らしの方に安心:食事の準備が難しい場合、昼食や夕食を自宅まで届けてくれる。
- 栄養バランスに配慮:管理栄養士が監修した献立が多く、噛む力や飲み込みに不安がある方への対応食も用意されている。
- 見守り機能も兼ねる:配達時に安否確認を行ってくれる。
- 利用頻度を選べる柔軟さ:週数回だけの利用から毎日の利用まで、ライフスタイルに合わせて選択できる。
※ただし、配食サービスの内容や頻度は自治体によって異なります。
どんな人が自治体の配食サービスを利用できるの?
主な対象者は、それぞれの自治体が定める基準によって異なります。
ただし、全国的な傾向として共通しているのは食事の準備が困難で、特に見守りが必要な方。
具体的な対象者の条件は、大きく3つに分けられます。
利用できる年齢や世帯の基準



自治体の配食サービスを利用できるかどうかは、年齢や世帯の状況によって決まります。
多くの自治体で重視されるのは「何歳か?」そして「誰と暮らしているのか?」という点です。
主な基準は以下のとおりです。
- おおむね65歳以上であること
- 一人暮らしの高齢者
- 高齢者のみの世帯(ご夫婦二人暮らしなど)
- 高齢者と同居していても、日中仕事などで不在がちになる家族世帯
- 高齢者と障害者のみが同居している世帯
つまり、「自分で食事の準備をするのが難しい」「日中に見守ってくれる人がいない」といったケースが対象になることが多いです。


身体・健康状態による基準
配食サービスは、単に高齢であるというだけではなく、「なぜ食事の準備が難しいのか」という理由が必要です。
代表的な条件としては、次のようなものがあります。
- 病気や身体の障害によって、調理や買い物が自力では難しい場合
- 栄養状態の改善や、安否確認を兼ねた見守りが必要な場合
つまり、「体力が落ちてきて台所に立つのがつらい」「買い物に出るのが大変」「食事が偏ってしまう」など、健康や安全面からサポートが必要と判断されるケースが対象です。


その他の条件
自治体によっては、以下のような追加条件が設けられていることもあります。
- 「要支援1〜2」または「要介護1〜5」の認定を受けていること
- 市民税が非課税の世帯や、低所得世帯であること
これらの条件は地域によって異なり、「介護認定が必要なケース」や「経済的に支援が必要な世帯」を対象にしている自治体もあります。
補足:介護認定をすでに受けている場合は、まずはお住まいの地域包括支援センターや担当ケアマネジャーに相談してみると安心です。


料金と補助
配食サービスは自治体ごとに内容や料金が大きく異なります。
ここでは東京・名古屋・大阪の例を紹介します。
対象となる方は「高齢者」「要介護認定者」「一人暮らし世帯」など、自治体によって基準が異なります。ここでは料金や利用回数を中心に比較します。
| 自治体 | 対象者 | 費用(目安) | 利用回数・頻度 | 特徴・補助制度 |
|---|---|---|---|---|
| 東京(港区) | 65歳以上の港区在住で、食事作りが困難な方 | 1食あたり320〜480円(事業者による) | 昼食か夕食を週7回まで | ・指定業者が宅配 ・昼食9:30〜12:30/夕食14:30〜18:00 ・配食時間の指定は不可 |
| 名古屋市 | 在宅の要介護者など | 食事代は全額自己負担+配食経費200円の1割〜3割(20〜60円)を負担 | 昼食か夕食を週7回まで | ・生活援助型、自立支援型、障害者自立支援の3つの配食サービスで構成 |
| 大阪市 | 要支援1〜2、要介護1〜5の方 など | 食事代+配食費は自己負担 年間総所得150万円以下の市民税非課税世帯 → 1食400円を超える部分について最大150円助成 | 週あたり利用回数を市が調整して決定 | ・非課税世帯は負担軽減あり |
※ここで紹介したのは一例です。
実際の利用条件や料金は、お住まいの自治体窓口で必ずご確認ください。
申請手続き方法



高齢者向けの配食サービスを利用するためには、まずお住まいの市区町村での申請が必要です。
自治体ごとに細かな違いはありますが、一般的な流れは次のようになります。
申請窓口での手続き
窓口は「市区町村役所の高齢者福祉課」や「地域包括支援センター」が中心です。
- 申請書
- 利用承諾書
- 利用調査票(アセスメント)
- 家族の勤務状況などを記載した書類(自治体によっては不要)
申請書は窓口でもらえるほか、自治体ホームページからダウンロードできる場合もあります。
調査や登録
- 一人暮らしの高齢者の場合は「一人暮らし登録」や「生活状況調査」を行うことがあります。
- この調査は「本当に配食支援が必要かどうか」を確認するためのもので、後のサービス内容に反映されます。
申請方法
- 多くの自治体では 窓口で直接提出しますが、郵送で受け付けているところもあります。
- 申請理由は、できるだけ具体的に記入しましょう。
例)「病気で調理が難しい」「買い物に行けない」など
利用開始までの流れ
- 申請後、自治体や委託された配食事業者から連絡があります。
- 配食日や時間帯の調整を行い、サービス利用がスタートします。
※手続きには時間がかかり、申請から開始までに3週間〜1ヶ月程度かかることがあります。
利用中の変更や停止
- 「曜日を変更したい」「食事内容を変えたい」といった場合は、自治体の窓口や配食業者に連絡すれば手続きできます。
- 状況が変わって助成対象外になった場合は速やかに自治体へ連絡が必要です。
例)「家族と同居になった」「調理ができるようになった」など
ポイント
自治体によって申請のフォーマットや提出先は異なります。
実際に利用を考える際は、必ずお住まいの市区町村の公式サイトや福祉課に確認 するようにしましょう。
介護認定をすでに受けている場合はまずはお住まいの地域包括支援センターや担当ケアマネジャーに相談する方が手続きがスムーズです。
メリットとデメリット
- 栄養バランスの管理:管理栄養士が監修したメニューの提供
- 調理の負担軽減:買い出しの手間がなく、親御さんの負担が大幅に減る
- 嚥下・咀嚼への配慮:噛む力や飲み込む力に合わせた「きざみ食」「やわらか食」「ムース食」などに対応しているサービスもある
- 安否確認:配達員が親御さんの安否確認の役割をしてくれる
- 費用:自炊と比較すると費用が高くなる
- 好みに合わない可能性:飽きが来ないように、メニューの豊富さが大切
- 保存方法:冷蔵・常温タイプでは消費期限が短い
- 配達エリアの制限:サービスによっては配達エリアが限られる場合がある
宅配サービスの選び方のポイント



最も重要なのは「健康状態に合っているか」「無理なく続けられるか」の2点。
自治体サービスは比較的お手頃で安心して利用できますが、利用回数や内容には限りがあることもあります。
そこで、ここからは民間の宅配サービスについても簡単にご紹介します。
健康状態



健康状態に合った食事かどうかをチェック。
宅配食を選ぶうえで一番大切なのは「親御さんの体調や病気に合った食事かどうか」です。
- 高血圧で塩分制限が必要
- 腎臓病や肝臓病でタンパク質制限がある
- 糖尿病でカロリー制限が必要
といったケースでは、一般的なお弁当では対応が難しいことがあります。
病院や栄養士に相談しながら、制限食に対応しているサービスを選ぶと安心です。
特に初めて宅配食を利用する場合は、事前に確認しておくと後悔がないでしょう。
食事の形態・量
高齢の方の中には、「自分の歯でしっかり噛めるから問題ない」という方もいれば、「入れ歯が合わず固いものは食べづらい」という方もいらっしゃいます。
また、年齢を重ねると食べる量が少しずつ減っていくのも一般的です。
チェックしたいポイントは次の2つです。
- 噛む力や飲み込む力に合わせて、やわらかさ形態が調整されているか
- 食事量を無理なく調整できるか
親御さんの体調や食欲に合わせて、無理のない形態や量を選ぶことが続けやすさにつながります。
保存方法
宅配食の保存方法は「常温・冷蔵・冷凍」の3つに分けられます。
特に自治体の配食サービスでは、配達員が安否確認を兼ねて手渡しする仕組みが多いため、常温や冷蔵で「その日のうちに食べきる」形式が一般的です。
一方で、民間の宅配食サービスには冷凍タイプが多く、まとめて受け取って必要なときに温めて利用できる便利さがあります。
- 自治体サービス:当日消費(安否確認あり)
- 民間サービス:冷凍保存が可能(安否確認なし、利便性重視)
親御さんに「安否確認を含めて見守りをお願いしたい」のか、それとも「自由にストックして食べたい」のかによって、選ぶサービスも変わってきます。
価格と継続性
毎日利用するとなると、1食あたりの価格はとても重要です。
送料込みでどのくらいかかるのかを確認しましょう。
- 自治体サービス:助成がある場合、1食あたり約300~500円と比較的安価。ただし自治体によって料金は異なるため、事前確認が必要です。
- 民間サービス(日替わり・冷蔵配達):1食あたり約500~800円程度。冷蔵で届くのでそのまま食べられる利点があります。
- 民間サービス(冷凍・まとめ買い):1食あたり約500~700円程度。別途送料がかかる場合が多いので注意が必要です。
また、注文頻度(週1回~毎日まで)や、スキップ・キャンセルがしやすいかどうかも、無理なく続けられるかを左右する大切なポイントです。
安否確認
自治体の配食サービスでは、食事の配達と同時に高齢者の安否確認をしてくれるケースが多くあります。
一人暮らしの親御さんにとっては、毎日の食事だけでなく「今日も元気に過ごしているか」を第三者が見守ってくれる安心感につながります。
一方で、民間の宅配弁当サービスでは安否確認が基本には含まれていないことが多く、あくまで食事提供が中心です。
そのため、安否確認も重視したい場合は、自治体サービスを優先的に利用するか、あるいは民間サービス+見守り機器や地域サービスの併用を検討すると安心です。
メニュー
食べることは日々の楽しみの一つです。
配食サービスを無理なく続けるためには、飽きがこないことがとても大切になります。
- メニューの更新頻度:毎週や数週間ごとに新しい献立に切り替わるかどうかを確認しましょう。
- お試しセットの活用:多くの民間サービスでは、初回限定のお試しセットや割引があります。少量で味や食べやすさを確認してから本格的に利用を始めると安心です
自治体サービスはどうしても献立の種類が限られてしまう場合がありますが、民間サービスでは和洋中や制限食など、幅広いメニューから選べるのが特徴です。
親御さんの好みや体調に合わせて選ぶと、食事の楽しみが続きやすくなります。


注文・問い合わせ
インターネットでの注文やメールでのやり取りは便利ですが、高齢の方にとってはハードルが高い場合もあります。
- 電話対応の有無:高齢者が自分で注文できるよう、電話での問い合わせ・注文が可能かを確認しておくと安心です。
- 家族のサポート:インターネット注文が中心でも、家族が代理で注文できる仕組みを整えておくとスムーズです。
- 自治体 vs 民間の違い:自治体は地域包括支援センターや福祉課などでの申し込みが中心。民間サービスは公式サイトや電話での注文が一般的です。
「問い合わせのしやすさ」は、継続利用のしやすさにも直結します。
親御さんの状況に合った窓口があるかどうかを確認しておくことが大切です。
決定のプロセス



配食サービスを選ぶときは、次のような流れで検討すると安心です。
最優先は自治体サービスの確認
まずはお住まいの市区町村が実施している配食サービスを確認しましょう。
自治体サービスは 安否確認が含まれていることが多く、費用も比較的安価 です。
制限食が必要な場合も、対応してもらえるかを確認しておくと良いでしょう。
代替案として民間サービスを検討
もし自治体サービスだけでは対応できない場合(例:腎臓病や糖尿病などで厳密な制限食が必要なケース)、民間の宅配サービスが選択肢となります。
特に冷凍食の定期宅配は、制限食に対応している会社も多く、買い物や調理が難しい家庭にとって心強いサポートになります。
自治体+民間の併用も視野に
自治体の配食サービスだけでは利用回数に制限がある場合もあります。
そんなときは、民間サービスを併用するのも一つの方法です。
民間サービスには制限食の対応が充実しているところも多く、冷凍保存できるお弁当ならストックしておけるので安心です。
生活スタイルや親御さんの健康状態に合わせて「自治体+民間」の両方をうまく取り入れることで、無理なく続けやすくなります。
実際のケースから見る配食サービスの利用例
配食サービスの利用は人それぞれの事情によって異なります。
私が病院で入院支援に関わるなかでも、次のようなケースをよく目にします。
- 調理が難しく、これまではスーパーのお惣菜や白米だけで済ませてい方。配食サービスを利用してからは、栄養バランスの取れた食事を安心して続けられるようになりました。
- 自治体のサービスを知り、1食は助成を受け、もう1食は自費で追加注文して家事を軽減している方。
- 訪問ヘルパーやデイサービスの利用日に合わせて、無駄のないように配食を調整している方。
また、私の友人のお父様は透析治療を長年続けておられ、厳しい食事制限が必要でした。
毎日家族が献立を工夫するのは大変ですが、民間の配食サービスを取り入れることで負担が軽くなり、安心して療養生活を送ることができています。
このように、制度やサービスを上手に活用することで、食事の準備がぐっと楽になり、家族も本人も快適に過ごせるようになります。
皆さんにもぜひ知っていただきたいポイントです。
私の両親は田舎で暮らしており、買い物も不便な環境にあります。
将来の親の介護を考える中で「良い宅配食はないかな?」と思い、実際に私自身が注文して試食してみました。
そのときの体験談をこちらの記事で紹介しています。


よくある質問
- 自治体の配食サービスは誰でも利用できますか?
-
基本的には高齢者の一人暮らしや、高齢者だけの世帯が対象です。ただし、条件は自治体によって異なるため確認が必要です。
- 自治体の配食サービスは安否確認もしてもらえますか?
-
多くの自治体では配達時に安否確認を兼ねています。ただし、地域によって実施状況が異なるため、事前に確認しましょう。
- 費用はどれくらいかかりますか?
-
助成がある場合は、1食あたり約300~500円と比較的安価です。
自治体ごとに設定が異なるため、事前に確認しておくと安心でしょう。
なお、民間サービスでは1食あたり約500~800円程度が目安となります。
- どこで相談するとよいですか?
-
介護認定をすでに受けている場合は、地域包括支援センターや担当ケアマネジャーに相談するとスムーズです。
介護認定がない場合も、市区町村の高齢福祉課などで相談できます。
- 制限食(糖尿病食や腎臓病食など)も対応していますか?
-
多くの自治体や委託業者が、塩分・カロリー・タンパク質の調整などに対応しています。
ただし対応できない場合もあり、その場合は民間サービスを利用すると安心です。


今日のまとめ
高齢者の在宅生活を支えるには、まず自治体の配食サービスを活用するのが安心です。
買い物や調理の負担が減り、火の取り扱いの不安も軽減されます。
さらに、栄養バランスの取れた食事が届くことで健康維持に役立ち、日中独居の方には安否確認も兼ねられる点が大きなメリットです。
例えば「週に数回は配食サービスを利用し、残りは自宅調理やデイサービスで補う」といった形で、無理なく継続することもできます。
介護認定を受けている場合はケアマネジャーへの相談がスムーズ。
そうでない場合も、市区町村の窓口で確認しておくと良いでしょう。
また、腎臓病食や糖尿病食などの制限があるケースでは、自治体の委託業者が対応していることもあるので、相談されるとよいでしょう。
ただし、利用回数に制限がある自治体もあるため、冷凍保存が可能な民間サービスを組み合わせておくと安心です。
冷凍宅配食をストックしておけば、必要な時にすぐ利用でき、家族の負担を減らしながら毎日の暮らしを支える心強い味方になってくれます。

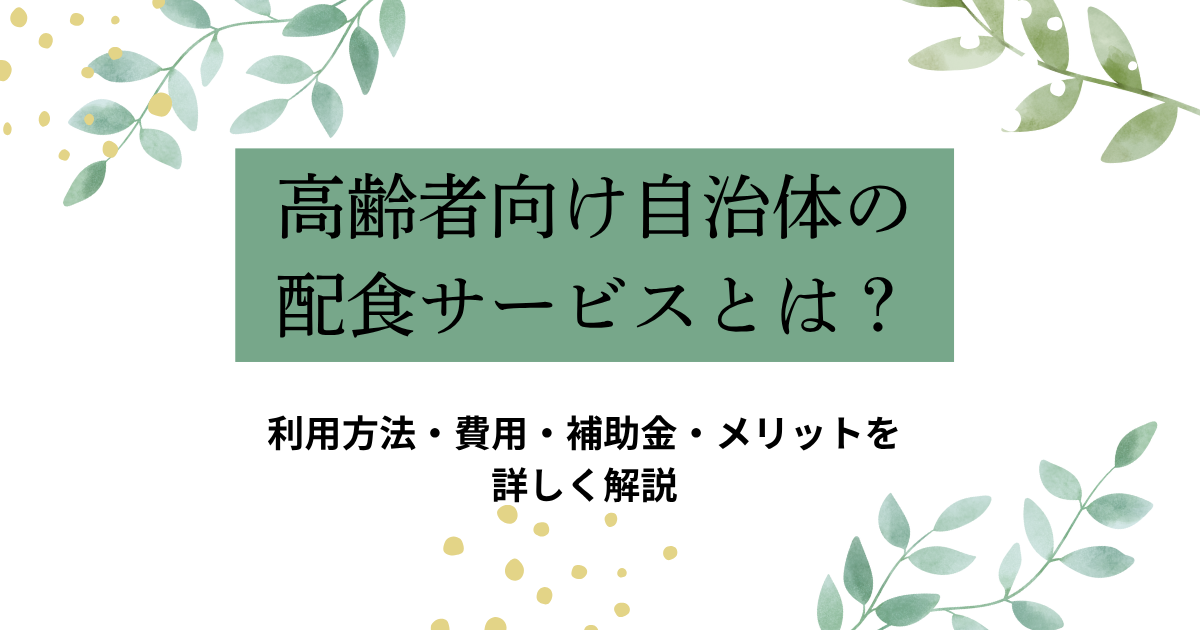
コメント