こんにちは。看護師として30年以上、医療と介護の現場に関わってきたさくらです。
今日もご家族の介護に役立つ内容をお届けしていきます。
親の入院は、ある日突然やってきます。
「昨日まで元気だったのに…」「退院したらどうなるのだろう?」と、戸惑いや不安を抱えるご家族は少なくありません。
そんな時、慌てずに動けるようにするためには、退院後の生活や介護保険制度の流れを前もって知っておくことが大切です。
この記事では、急な入院への備えから退院後の生活の選択肢、介護保険制度の申請方法、そして仕事との両立までを整理しました。

私は急性期病院で30年以上、臨床現場で患者さんやご家族と向き合ってきました。
現在は入退院支援の業務に携わり、日々ご家族からの相談を受けています。
その経験をもとに、現場でよく聞かれる声やリアルな対応策を交えて解説します。
読んでいただくことで「自分だけじゃない」と安心でき、実際に動き出すための具体的な一歩が見えてくるはずです。
少しでも、あなたとあなたの家族のお役に立てれれば幸いです。
親の急な入院への備え(平時から)
親の入院はいつ起こるか分かりません。平時から「書類」「連絡体制」「親の意向」を整理しておくと、救急や入院手続きの負担が大きく軽減されます。

以下、よくいただく質問内容です。一緒に見ていきましょう。
よくある質問(FAQ)
- 普段から用意しておくものはなんですか?
-
• 入院歴・手術歴・持病や通院先をまとめたメモ
• 健康保険証・介護保険証・お薬手帳
• 緊急時の連絡先リスト
これらを一式そろえてセットで保管しておくと、救急搬送や入院手続きがスムーズに進みます。
▼親の現状をどう把握するか(入院前の準備リスト)詳しくはこちらの記事から
- キーパーソンとはなんですか?
-
キーパーソンとは、家族側の窓口のことです。医療方針の調整や重要な判断を担う「家族の代表」です。いざという時に最も連絡がつきやすい人を、第一連絡先(キーパーソン)として決めておくと安心です。
▼家族の中で誰がキーパンソンに最適?詳しくはこちらの記事から
親が突然入院!落ち着いて対応するために知っておきたい3つの準備
- 親の意向確認は何を聞けばよいですか?
-
• 自宅で暮らしたいか、施設も選択肢に入れるのか
• 急変時の救急搬送や延命治療についての考え方
事前に少しずつ話し合っておくと、慌てず対応できます。
▼詳しくはこちらの記事から
親の介護が突然必要に!介護方針・希望の確認ポイント【第2話】
▼延命治療について、下記ホームページの内容を参考にしてみてください。
下記ホームページの内容を参考にしてみてください。
アドバンス・ケア・プランニング(ACP)ー人生会議ー
「▶詳しくはこちら」https://www.tokyo.med.or.jp/citizen/acp
印刷して使える「病歴メモ&緊急連絡先シート」をご用意しました。
親の急な入院に備えて、必要な情報を一枚にまとめておけます。
ぜひダウンロードして、ご家庭で役立ててください。
看護師として感じる現場のリアル
予定入院の手続きであっても、ご家族が同伴していても、親御さんの現状を正確に把握できていないケースはとても多いのが実情です。
実際、私が1か月に120人ほど対応する中で、メモを持参される方は年間でほんの数人程度にすぎません。
緊急入院ではさらに時間的な余裕がなく、状況はもっと逼迫します。
だからこそ、普段から病歴や手術歴等のメモを残しておくこと、お薬手帳管理が、本人やご家族を守る大切な準備といえるでしょう。
ぜひ「病歴メモ」を日常に取り入れていただければ幸いです。
介護保険とは?申請方法を解説
※ここでは介護保険の基本を簡潔に紹介しています。
より詳しい申請方法・サービスの流れなどは、関連記事で解説していますのであわせてご覧ください。

以前にも触れましたが、「介護保険」という言葉は知っていても、仕組みや申請の流れは分かりにくいものです。
ここでは、介護保険の基本を整理してお伝えします。
介護保険とは、高齢になって体力が落ちたり、病気で一人で生活することが難しくなった時に、公的な制度としてサポートを受けられる仕組みです。
例えば「親が転倒して入院してしまった」「体調を崩して一人暮らしが難しくなった」そんなときに、介護保険のサービスを使うことで自宅や施設での生活が続けやすくなります。
ただし、介護保険を利用するためには「介護が必要な状態です」と認定を受けることが前提。
これを「介護認定」と言います。
▼介護保険についての詳しく知りたい方はこちらの記事で紹介。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは
介護サービスを利用する際には、ケアマネジャー(介護支援専門員)が重要な役割を担います。
ご本人やご家族と話し合いながら「ケアプラン」という計画を作成し、必要なサービスを調整してくれる存在。
「どんなサービスをどのくらい使えるのか?」といった不安も、ケアマネジャーが窓口になって支えてくれるので、安心して制度を利用できます。
▼ケアマネジャーの役割についての詳しく知りたい方はこちらの記事で紹介。
ケアマネジャーの役割とは?失敗しない選び方・変更方法を看護師がわかりやすく解説
よくある質問(FAQ)
- 介護保険はどこで申請できますか?
-
申請先はお住まいの市区町村ですが、初めての場合は近くの「地域包括支援センター」に相談することをおすすめします。
相談員が同席してくれることで安心でき、書類の不備があってもその場で修正可能。
申請相談から代行申請まで依頼できる場合もあります。
▶介護保険対象者、相談窓口について詳しく知りたい方はこちらの記事で紹介。
- 介護保険申請に必要な書類はなんですか?
-
年齢によって異なります。
• 65歳以上の方:申請書(介護保険要介護・要支援認定申請書)、介護保険被保険者証
• 40歳~64歳の方:健康保険証(医療保険証)を一緒に提出してください。
※市区町村の窓口や公式ホームページから申請書をダウンロードできます。
※マイナンバーカードや運転免許証など身分証明書も必ず持参しましょう。
▶介護保険申請に必要な書類・サービスの流れについて詳しく知りたい方はこちらの記事で紹介。
- 介護認定が下りるまでにどのぐらいの時間がかかりますか?
-
申請から結果通知まではおおよそ30日程度(約1か月)が目安です。
調査員がご本人に聞き取りや訪問調査を行い、主治医の意見書とあわせて審査されます。
※調査や意見書の回収状況によっては、もう少し時間がかかることもあります。
看護師とし現場でよく聞く声
今まで元気に過ごしていたのに、突然の入院。
退院しても、もう元の生活に戻れない…。
「このまま自宅に帰ってもどうしたらいいのか分からない」というご家族は少なくありません。
実際にご家族からは、
- 誰が親の面倒を見るのか?
- 同居していない、あるいは遠方で暮らしている
- 親が高齢二人暮らしで、今後の生活が心配
- 自分たちも仕事や生活があり、すぐに動けない
といった相談をよく受けます。
こうした状況は、いつどの家庭でも起こり得るでしょう。
だからこそ、普段から「介護保険制度」や「利用できるサービス」を知って備えておくことが大切です。
制度をうまく利用することで、ご家族の負担を減らし、安心して親御さんを支えることができます。
介護保険で利用できるサービスまとめ
居宅・地域密着型・福祉用具・住宅改修を解説
介護サービスを利用するには、まず「介護度」と呼ばれる区分で、どのくらいサポートが必要かを判断します。
区分は「要支援1・2」と「要介護1〜5」の7段階。
数字が大きくなるほど、生活の中で手助けが必要になります。
- 例えば「最近つまずきやすくなった」くらいなら要支援
- 「食事やトイレも一人では難しい」となると要介護度が高め
サービスを利用するときは自己負担が必要です。
原則は1割ですが、収入が多い方は2〜3割になることもあります。
同じ1割負担でも、介護度が高ければその分使えるサービス量が多くなる仕組みです。
▶詳しい基準や費用についてしりたい方は、厚生労働省の公式ページをご覧ください。
よくある質問(FAQ)

- 居宅サービスとはなんですか?
-
居宅サービスは、要支援・要介護の方が住み慣れた自宅で生活を続けられるように支援するサービスです。
代表的には以下があります。
- 訪問介護(ヘルパーによる生活援助や身体介護)
- デイサービス(通所介護)
- ショートステイ(短期入所) など
▼居宅サービスについて詳しく知りたい方はこちらの記事で紹介。
- 地域密着型サービスとはなんですか?
-
地域密着型サービスは、お住まいの市区町村が主体となって運営する介護サービスです。身近な地域で受けられることが特徴で、利用者は顔なじみのスタッフから継続的支援を受けやすくなります。
主なサービスには、以下のようなものがあります
- 地域密着型デイサービス(地域密着型通所介護):少人数で家庭的な雰囲気の中、入浴・食事・機能訓練などを受けられる。
- 認知症対応型デイサービス・グループホーム:認知症の方に特化し、専門スタッフが日常生活をサポート。
- 夜間対応型訪問介護や定期巡回・随時対応型訪問介護:夜間や緊急時にも支援が受けられる体制。
- 看護小規模多機能型居宅介護:医療ニーズの高い方でも「通い」「泊まり」「訪問介護・看護」を組み合わせて利用できる。
▼地域密着型サービスについて詳しく知りたい方はこちらの記事で紹介。
- 福祉用具は介護保険で利用できますか?
-
はい、介護保険を使って「レンタル」や「購入」ができます。
対象は13品目に限定されていて、手すりやスロープなどは要支援の方でも利用可能、介護ベッドや車いすなどは要介護2以上の方が対象です。
- 要支援~要介護5で利用可:手すり、歩行器、歩行補助杖、スロープ、排泄関連用具(尿器など)
- 要介護2以上で利用可:特殊寝台(介護用ベッド)、車いす、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト、認知症老人徘徊感知機器 など
▼「介護保険でできる福祉用具貸与」「特定福祉用具販売」について詳しく知りたい方はこちらの記事で紹介。
- 介護保険で住宅改修は利用できますか?
-
はい、介護保険では手すりの取り付けや段差の解消など、自宅を安全に暮らせるようするための住宅改修が対象になります。
上限は20万円(1割~3割の自己負担)までで、要支援・要介護の認定を受けている方が対象です。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消(スロープ設置など)
- 滑り防止のため床材変更
- 扉の取り替え(引き戸など)
- 洋式便器への交換
▼「住宅改修」について詳しく知りたい方はこちらの記事で紹介。
看護師として現場で感じること
ご家族と離れて暮らす高齢の方、一人暮らしやご夫婦だけで過ごしている方は少なくありません。
「まだ大丈夫」「周りに迷惑をかけたくない」という思いから、介護保険の申請をなかなかされない方も多く見受けられます。
また、「デイサービスは自分には必要ない」と考える方もいますが、実際には体力や記憶力の低下を早めに支える場として、とても役立つでしょう。
ご家族としても「最近、体力が落ちてきた」「物忘れが気になる」と感じたときこそ、地域包括支援センターに一度相談してほしいと強く思います。
ケアマネジャーさんと一緒に考えることで、その方に合ったサービスが見つかり、安心した生活につながるでしょう。
「退院後の生活の選択肢」在宅介護か施設入所か
先日まで元気にしていた親が、突然の入院。
命に関わる急性期を乗り越えて「これで一安心」と思った矢先に、主治医から告げられるのは…。
「状態が安定したので、転院になります」
「え?治るまでこの病院に置いておいてくれないの?」
多くのご家族がそう感じるようです。
しかし現実には、急性期医療を担う病院は「長期療養の場」ではありません。
治療の役割を終えると、回復期リハビリ病院や地域包括ケア病院へと移り、その後は在宅介護か施設入所かの選択を迫られることになります。
だからこそ、いざという時に慌てないために、退院後にどんな選択肢があるのか、あらかじめ知っておくことがとても大切です。
よくある質問(FAQ)

- 病院から「退院前カンファレンスに参加してください」と言われました。これは何ですか?
-
退院前カンファレンスとは、患者さんが退院後も安心して生活できるように、病院の医療スタッフと家族、地域のケアマネジャーや訪問看護師などが集まり、今後の療養方針や必要なサービスについて話し合う場です。
- ご本人の病状や生活の見通し
- 自宅に戻るのか、施設に行くのか
- 必要となる介護サービスや医療サポート
- 退院までに準備しておくこと
退院後の暮らしに直結する大事な会議なので、ご家族が参加して「不安なこと」「希望する生活スタイル」を伝えることがとても大切です。
- 父が要介護認定を受けました。母は元気ですが、ヘルパーさんに家の掃除や買い物、食事をお願いできますか?
-
介護保険サービスは、要介護認定を受けた本人の生活支援に限られます。
そのため、元気なお母さまの分の掃除や食事づくりを、ヘルパーさんにお願いすることはできません。
ただし、介護を受けるお父さまの生活を支えるために必要な範囲であれば、掃除や調理などの支援は利用できます。
ご夫婦二人分の家事全般を頼みたい場合は、介護保険外のサービス(家事代行や配食サービスなど)を活用すると安心です。
たとえば、宅配食なら栄養管理されたメニューを選べて、介護される方も元気なご家族も一緒に利用できます。
▼詳しくはこちらで解説しています
【ウェルネスダイニング】高齢者におすすめ宅配食を看護師が実食
- 高齢独居のため、施設入所も検討中です。施設を検討する場合、どんな種類がありますか
-
介護施設にはいくつかの種類があり、介護度や費用、生活スタイルによって選択肢が変わります。主なものは以下のとおりです。
- 特別養護老人ホーム(特養):要介護3以上の方が対象。費用は比較的安価ですが、待機者が多い傾向。
- 介護老人保健施設(老健):在宅復帰を目的とし、医療ケアやリハビリが充実。原則3〜6か月の短期入所。
- 介護医療院:医療と介護の両方が長期的に必要な方を対象とする施設。
- 有料老人ホーム:民間運営で「介護付き」「住宅型」「健康型」などがあり、費用やサービスの幅が広い。
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住):比較的自立している方向け。安否確認や生活相談サービス付き。
施設によって 対象者・費用・生活の自由度 が大きく異なるため、見学や相談を重ねて検討することが大切です。
▼さらに詳しい特徴や選び方はこちらの記事で紹介。
- 両親を施設に入れる選択肢に対し、罪悪感を感じます。この判断は良かったのでしょうか?
-
介護のために施設入所を選ぶと、多くのご家族が「本当にこれで良かったのか」と罪悪感を抱きがちです。
ですが、施設に入所することは「家族を見放すこと」ではありません。
むしろ、ご本人が安全に暮らせる環境を整え、家族が安心して寄り添える時間を持つための選択です。
補足説明
- 実際に現場でも「施設に入ってから親子関係が穏やかになった」「介護の負担が減り、笑顔で会えるようになった」といった声をよく耳にします。
- 大切なのは「入所=終わり」ではなく、その後も定期的に面会したり、外出を一緒に楽しんだりすることで、親孝行を続けることはできます。
▼関連記事で詳しく解説しています。
現役看護師がお伝えしたいこと
急な入院で急性期の治療を終えたあと、多くの場合は「転院の話」と「介護申請」が同時に進みます。
ご家族にとっては、心も体も休まる間もなく「これからどうすればいいのか」と不安が押し寄せますよね。
現場でも「私たちにも生活があるのに、どうにかしてください」といった切実な声をいただくことは少なくありません。
こうしたときに、少しでも落ち着いて対応できるようにするためには、介護保険制度を理解し、必要なサービスをうまく活用することが大切です。
介護は家族だけで背負うものではなく、病院や地域の支援を含めた「チーム」で取り組んでいくもの。
制度を知っておくことが、ご本人にも家族にも安心をもたらす第一歩になります。
親の介護と仕事の両立│介護休業制度の基本と活用法

介護離職という言葉を耳にしたことはありますか?
介護離職とは、家族や親の介護を理由に、仕事を辞めざるを得なくなること。
特に50〜54歳の働き盛り世代では、仕事と介護の両立が難しくなるケースが多く、介護負担が大きいことが調査でも明らかになっています。
キャリアの途中で仕事を辞めることは、経済的にも精神的にも大きな影響を及ぼすものです。
しかし、介護休業制度や介護休暇といった公的な制度を知って活用すれば、仕事を続けながら介護と両立できる可能性があります。
大切なのは「制度を知らなかったから選択肢がなかった」とならないこと。
正しい情報を押さえておくことで、介護と仕事の両立を支える力になるでしょう。
よくある質問(FAQ)
- 介護休業と介護休暇の違いはなんですか?
-
「介護休業」は、最長93日までまとまった期間を休む制度です。
一方で「介護休暇」は、通院の付き添いや一時的な介護などのために、1日または半日単位で取得できる制度です。
目的と使い方が異なるので、状況に応じて使い分けましょう。
- 介護休業と休暇の対象者は誰ですか?
-
配偶者、父母、子どもに加えて、同居・扶養している祖父母や兄弟姉妹、孫、義父母なども対象になります。
対象範囲は広いため、自分の家族が当てはまるかどうか確認しておくと安心です。
- 介護休業中は給料が出ますか?
-
原則として無給ですが、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。
支給額は休業前賃金の67%程度です。
会社によっては独自の有給制度を設けている場合もあるので、勤務先の就業規則を確認してみましょう。
- 介護休業を申請するにはどうすればよいですか?
-
勤務先に所定の申請書を提出して行います。
休業開始日の2週間前までに申し出るのが一般的です。
スムーズに手続きを進めるためには、早めに上司や人事担当者へ相談しておくと安心です。
▼「介護休業制度・介護休暇等」について詳しく知りたい方はこちらの記事で紹介。
介護で仕事を辞めるべき?離職を防ぐために知っておきたい制度と選択肢
現役看護師がお伝えしたいこと
臨床現場で長く働いてきた中で、「介護と仕事の両立」に悩まれるご家族を数えきれないほど見てきました。
急な入院から始まり、退院後の生活の準備、介護保険の申請、そして日々の生活支援…。
ご家族は「自分の生活もあるのに、どうすれば良いのか」と、心身ともに追い詰められる場面が少なくありません。
しかし、制度を知り、早い段階でケアマネジャーや職場と連携していくことで、介護と仕事を両立できた方も多くいらっしゃいます。
実際に、私の職場でも介護休業制度を利用し、離職を回避できたケースがありました。
介護は家族だけで抱えるものではありません。
病院の医療スタッフ、地域のケアマネジャーや相談窓口、そして公的制度を組み合わせて、一緒に取り組むものです。
ご自身のキャリアや生活を守りながら、親の介護に向き合うためにも、「一人で背負わない」という視点をぜひ持っていただきたいと思います。

今日のまとめ
親の急な入院に慌てないためには、日頃から親御さんの体調変化や希望を確認しておき、介護保険制度や退院後の選択肢を理解・準備しておくことが欠かせません。
こうした備えが、ご本人の安全な生活を守り、家族の介護負担を軽減し、仕事と介護を両立させる第一歩となります。
制度やサービスを知らないままでは、退院時に家族が過度な負担を背負い、介護離職に追い込まれるリスクもあります。
逆に、事前に情報を得て備えておけば、親御さんが安全に暮らせる環境を整えられ、家族の生活も守ることができるでしょう。
例えば、介護保険の申請方法や相談窓口を早めに確認しておくこと。
利用できる介護サービス(訪問介護・訪問看護・デイサービスなど)を知っておくこと。
そして退院後に「在宅介護」か「施設入所」かを、親御さんの希望を尊重しながら検討しておくこと。
これらを実践するだけでも、心の余裕と選択肢が大きく変わるでしょう。
介護は突然始まるものですが、知識と準備があれば「安心して暮らす親」「無理をせず支える家族」「離職を防ぐ働き方」につながります。
どうか普段から少しずつ理解を深め、備えておきましょう。
そして、「自分ひとりで抱え込まなくても大丈夫」ということを忘れないでください。
少しでも、あなたとご家族のお役に立てれば幸いです。

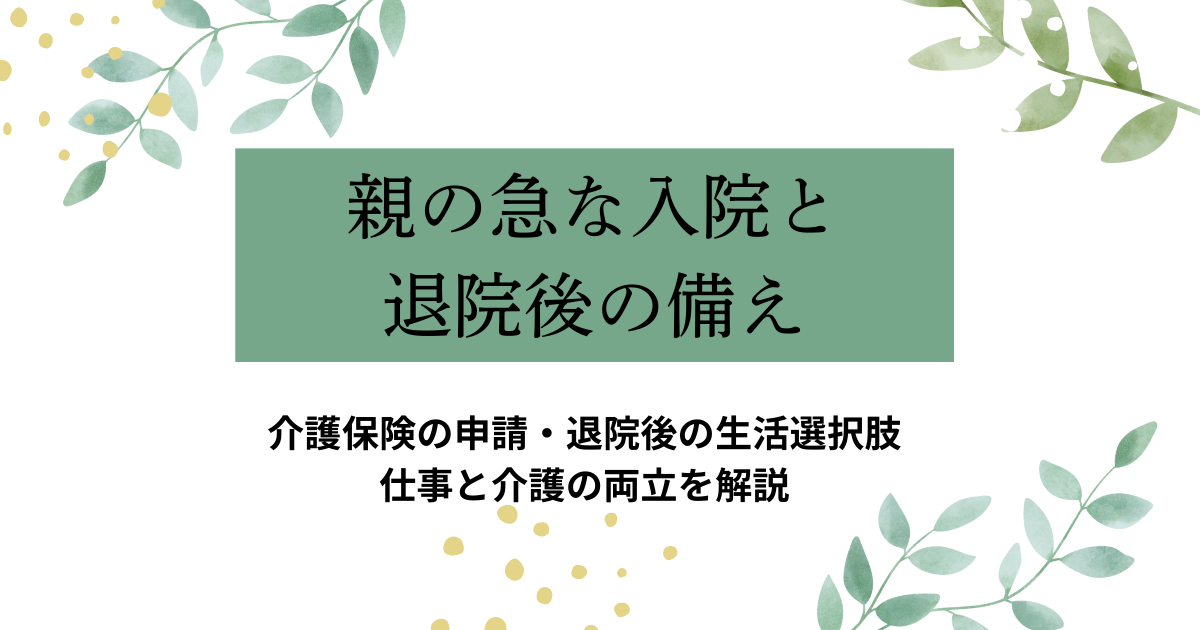
コメント