こんにちは。看護師として30年以上、医療と介護の現場に関わってきたさくらです。
前回は「施設」という選択肢を考える内容をお届けしました。
今回は少し視点を変えて、「親を施設に入れるときに感じる罪悪感」についてお話しします。
介護は長期戦になることが多く、家族の負担が大きくなりやすいもの。
家族みんなで支え合えれば理想ですが、実際には誰か一人に大きな負担がかかってしまうことも少なくありません。
頑張りすぎた結果、家族間にすれ違いや感情のぶつかり合いが起こり、関係性が悪化してしまう…。
そんな声も、現場で何度も聞いてきました。
「親の急な入院で、在宅での介護が難しくなった。」
「50代、自分の仕事や家庭のこともあり、どうしても物理的に支えきれない。」
など、施設入所を決める理由は人それぞれです。
でも、いざ施設への入所を決めたとき…。
「親を見捨てたように感じてしまう。」
「この判断は本当に正しかったのだろうか。」
「親は納得してくれたのかな…」
そんなふうに、さまざまな思いが交錯し、罪悪感を抱えてしまう方も少なくありません。
この記事では、罪悪感とどう向き合うか、そして施設入所を前向きに考えるヒントをお伝えします。
「施設という選択肢が間違いではなかった。」と納得できるような考え方や、施設入所のメリット、今後の親御さんへの関わり方をお伝えします。
このブログを読んで、少しでも心が軽くなってもらえたら幸いです。
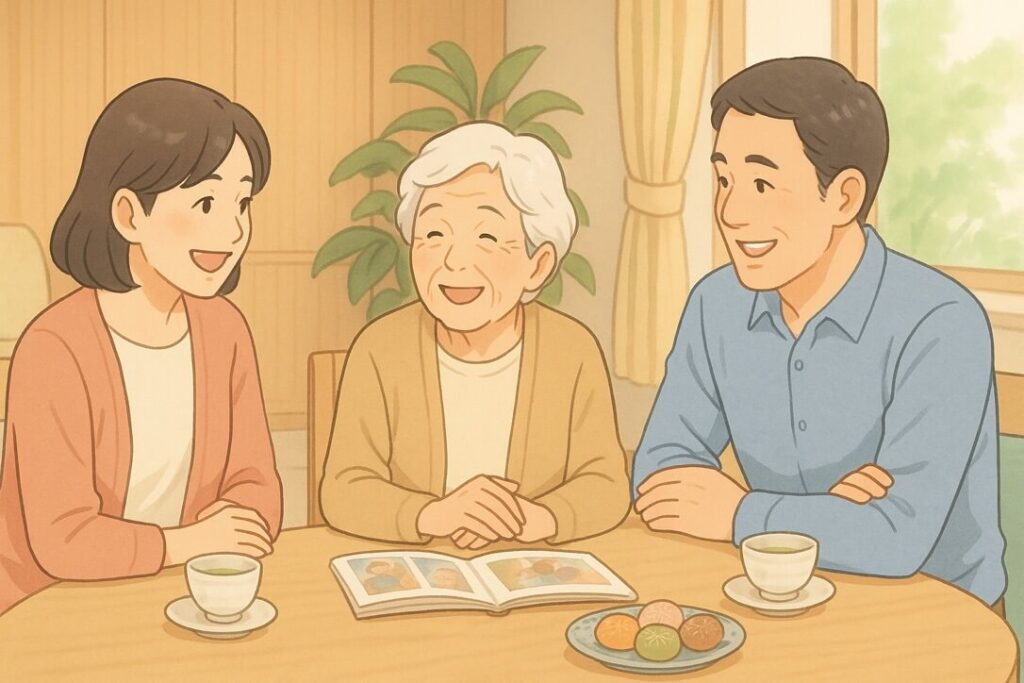
なぜ罪悪感を抱くのか
日本では今もなお、「親の面倒は子どもが見るべき」という価値観が根強く残っているように感じます。
こうした文化的・社会的な背景から、「親を最期まで自宅で看るのが当たり前」「それが親孝行」
というプレッシャーが、無意識のうちに私たちの心に重くのしかかってくるのかもしれません。
「もっと頑張れたのでは…」
「親は自宅で過ごしたかったのではないか…」
「自分は親不孝だったのでは…」
そんなふうに、自分を責める気持ちになってしまう方も、少なくないのではないでしょうか。
罪悪感への向き合い方
「罪悪感」という感情。
それは、親御さんを大切に思う気持ちから生まれる、ごく自然なものです。
決して悪いことではありません。
ですが、その感情にとらわれて、自分自身を責めたり、苦しんだりすることは避けたいものです。
- 介護の限界:体力的・精神的な負担が限界を迎えることもある。
- 安全の確保:家族には仕事があり、24時間体制の介護は難しい場合も。特に老老介護では無理が生じやすい。
- 親御さんのQOL(生活の質):専門職によるリハビリやレクリエーション、他者との交流により生活にハリが生まれる。
- 施設入所がゴールではない:親孝行の形を「変える」という選択。
- 自分や家族の生活を大切にする:介護に追われて自分自身を見失わないため。
親を想うその気持ちは、とても優しく尊いものです。
でも、その気持ちに縛られて「罪悪感」ばかりを抱えてしまっては、本末転倒です。
施設は「親を手放す場所」ではありません。
「親をプロに託し、安全で豊かな暮らしを送ってもらうための場所」なのです。
施設入所のメリット
施設入所には、在宅介護では得られない多くのメリットがあります。
介護のプロフェッショナルが、24時間体制で常駐している安心感も大きな特徴です。
- 身体的・精神的な負担軽減:一人で抱え込む介護の重圧から解放される。
- 緊急時の対応がスムーズ:急な体調不良や転倒時にも迅速に対応可能。
- 新しいつながりが生まれる:同世代の入所者と交流し、孤独感の軽減。
- 社会参加の機会がある:季節ごとのイベントやレクリエーションに参加できる。
- 生活の質(QOL)の向上:リハビリ・栄養管理・清潔な住環境が整っている。
- 家族の関係性が改善しやすい:介護の負担が軽くなることで、心にゆとりが生まれる。

施設入所後も親孝行は続けられます
施設に入所したからといって、親孝行ができなくなるわけではありません。
むしろ、施設という安心できる環境があるからこそ、ご家族とのやりとりが穏やかに、あたたかくなることもあります。
たとえば面会時に、施設での出来事を一緒に聞いたり、近況を報告することも立派な親孝行です。
「子どもが自分を気にかけてくれている」
その気持ちだけで、親はうれしく感じるものです。
また、施設のイベントに一緒に参加したり、外出の計画を立てたりするのも良い方法です。
近所での買い物や食事でも、親御さんにとっては大切な「心の交流」になります。
無理のないかたちで関わりを続けることが、親子にとっての新しい時間の共有となるでしょう。
親が施設入所を嫌がったらどうするの?
「絶対に入りたくない。」
「家で死にたい。」
「そんなところに入れるなんて、冷たい。」
親がそう言うと、子どもとしては心が揺れますよね。
でも、大切なのは「話し合いをあきらめないこと」だと思います。
親がなぜ施設を嫌がるのか、その背景には「不安」「誤解」「寂しさ」「誇り」「過去のイメージ」など、さまざまな気持ちが隠れています。
まずは否定せずに聞く
親の気持ちをまずは受けとめること。
「そう思うんだね」と、頭ごなしに否定せず、寄り添って聞くことが、信頼の土台になります。
その上で、
- なぜ施設が嫌なのか?
- 何が一番不安なのか?
- どんな暮らしなら安心できるのか?
を、少しずつ話し合ってみましょう。
子の気持ちも、ていねいに伝える
親の思いを尊重しながら、自分の気持ちも正直に伝えることも大切です。
「ひとりにしておくのが心配なんだ」
「仕事との両立が難しくなってきた」
「できるだけ穏やかに関わりたいと思っている」
そんな想いを、怒らず、責めず、正直に伝えるのがコツです。
見学・体験入所・パンフレットなどの提案も
「一度見学だけでも行ってみない?」
「短期間だけ試してみようか」
「パンフレットを一緒に見てみよう」
いきなり結論を出さず、小さな提案から始めてみるのも一つの方法です。
施設=「終の住処」という重いイメージではなく、
「日中の安心な居場所」や「一時的なサポート」として伝えていくと、親の受け入れ方も変わってくるかもしれません。
友人の事例
私の友人Aさんのお話です。
お父様をがんで看取り、パーキンソン病のお母様と二人暮らしをされていたAさん。
とても母親想いの方で、仕事と両立しながら在宅介護を続けていました。
会社が近かったこともあり、毎日手作りのお弁当を置いて、お昼休みに帰宅しては、様子を見て声をかけていたそうです。
日常生活はほぼ自立されていたお母様も、年々筋力が低下。
やがてトイレに行くことさえ難しくなってきました。
ヘルパーさんに支援をお願いしながら、在宅での介護を続けていましたが、
「このままでは、母と十分に向き合えない。」
「でも、生活のために仕事を辞めるわけにもいかない。」
そう悩む日々が続きました。
担当のケアマネジャーさんから、
「在宅介護の限界かもしれませんね。」「施設入所も選択肢のひとつでは?」と勧められます。
迷いながらも、Aさんは施設入所を決断しました。
けれど、当初は「母を手放すようでつらい」
「自分で世話をしてあげられないことが申し訳ない」と、強い罪悪感に悩まされていたそうです。
しかし、Aさんは「親孝行のかたちを変える」と心に決め、それから毎日、欠かさず面会に通うようになりました。
お母様のそばで、たわいのない日常会話を交わす。

それが新しい親子の関わり方となっていったのです。
施設での暮らしにも徐々に慣れていき、スタッフの方々との信頼関係も築かれていきました。
おしゃべりが大好きなお母様は、スタッフの皆さんからもとても愛されていたそうです。
やがて、お母様は肺炎でお亡くなりになりましたが、Aさんは最後にこう話してくれました。
「後悔のない介護だったと思えています。」

まとめ:看護師として、あなたに伝えたいこと
仕事と介護の両立。
どちらも大切にしたいのに思うようにいかず、親を大切に想っているのに、イライラをぶつけてしまい、関係が悪くなってしまう…。
そんな経験をした方も、少なくないのではないでしょうか。
でも、介護は「がんばり続けること」だけが正解ではありません。
限界を迎える前に、施設という選択肢を考えることも、愛情のある行動のひとつです。
私自身、看護師としてたくさんのご家族を見守ってきました。
また、友人Aさんのように、「親孝行のかたちを変える」という選択で、悩みから解放され、親子関係がより穏やかになったケースも数多くあります。
施設に入所することで得られることは、たくさんあります。
- ご自身の体や暮らしを守ることができる
- 親御さんは、安全な環境で専門職のケアを受けられる
- リハビリ・栄養・衛生・交流などを通じて、生活の質(QOL)が高まる
- 無理のない距離感で、笑顔で関われる“新しい親孝行”が始まる
「これでよかったのかな」と迷いながらも、家族を想って選んだその決断は、きっと間違っていません。
どうか、ご自身を責めずに…。
そして、あなたとご家族にとって、心が少しでも軽くなる道が見つかりますように。
ご自身の健康や暮らしも大切にしながら、親御さんにも安全で穏やかな環境を。
そんな願いを込めて、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。
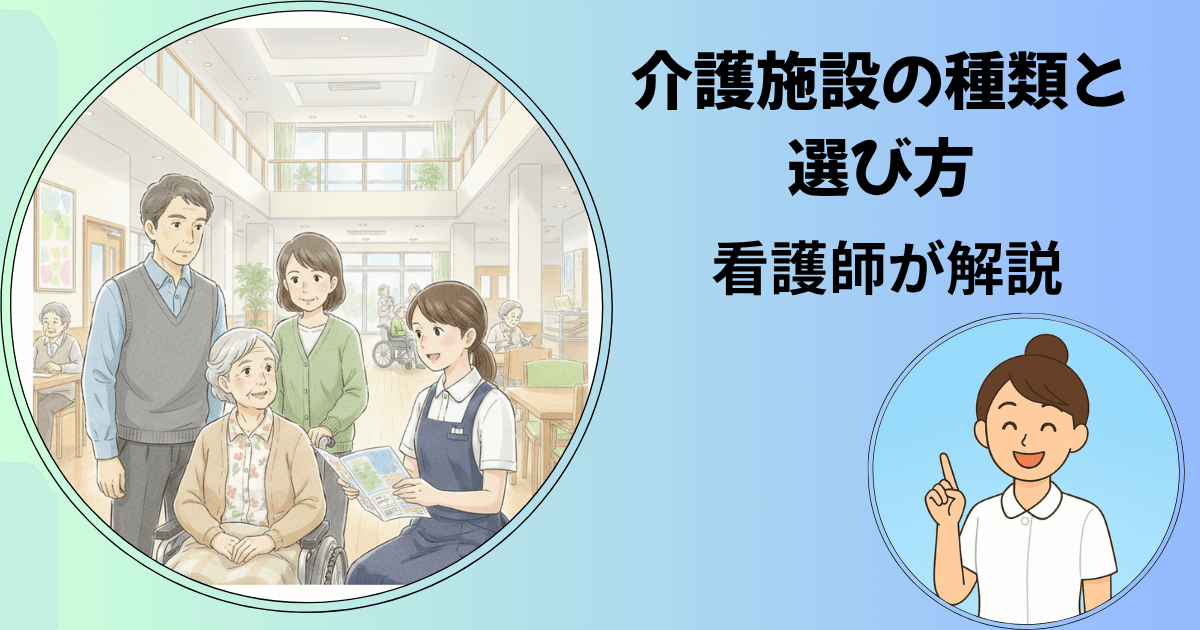
次回予告
「仕事を続けながら、親の介護なんてできるの…?」
実際、介護をきっかけに仕事を辞める「介護離職」は年々増えています。
次回は、介護離職を防ぐために、今からできる備えや活用できる制度について、看護師として、そして働く世代の一人としてお届けします。

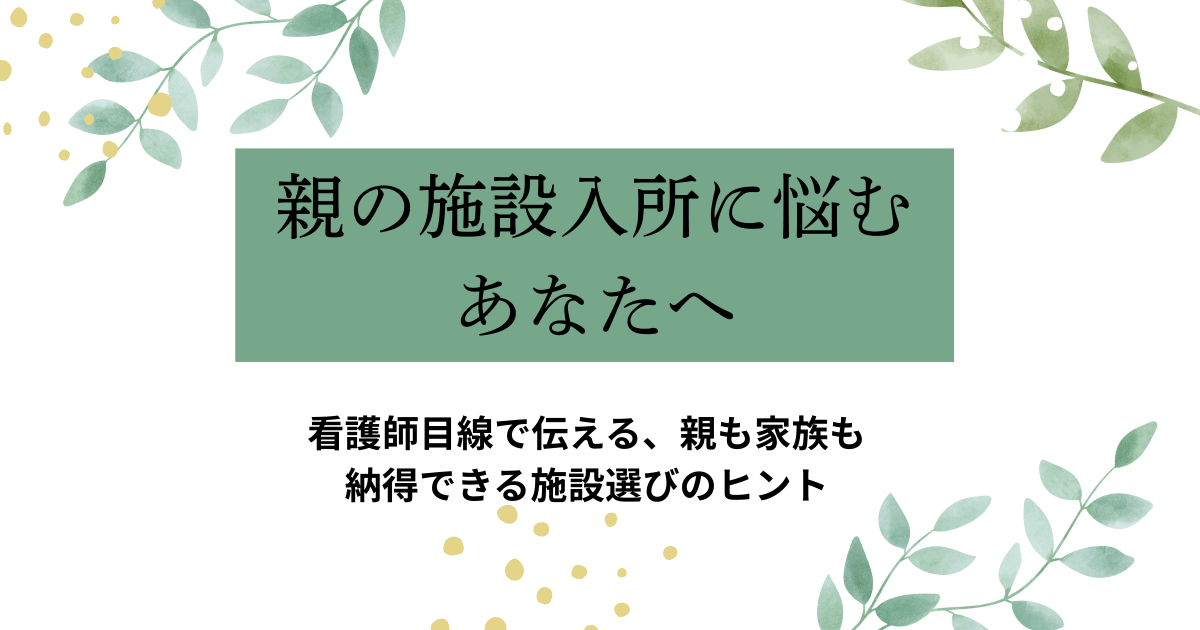
コメント