こんにちは。看護師として30年以上、医療と介護の現場に関わってきたさくらです。
子育てを終え、仕事と両親のことに向き合う日々を送っています。
50代を迎えた今、「つい自分のことは後回しに…」と感じている方も多いのではないでしょうか?
特に親の健康や介護に気を取られ、自分の体調変化に気づくのが遅れがちな年代です。
更年期は心身にさまざまな変化が起こりやすく、体調を崩しやすい時期とも言われています。
※一般的に閉経をはさんだ前後5年間、合計10年間を「更年期」と呼びます。
実際に、私の勤務する病院の相談室では、患者さんやご家族からこんな声をよく耳にします。
「こんなに進行してしまう前に、健診を受けておけばよかった」
「健診のおかげで早期発見できて本当に助かりました」

こうした言葉を聞くたびに、「自分の体を守るのは、自分しかいない」という思いを強くします。
健康を維持することは、親を支えることにも、自分の人生を楽しむためにも欠かせません。
この記事では、私自身の体験も交えながら、50代からの健康診断の大切さについてお伝えします。
読み終えた後、「行ってみようかな」と一歩踏み出すきっかけになれば嬉しいです。
50代が健康診断を受けるべき理由とは?
日本人の死亡原因の約5割は、がんや心臓病、脳卒中などの生活習慣病によるものと言われています。
生活習慣病とは、食習慣・運動不足・休養不足・喫煙・飲酒など、日常の生活習慣が原因で発症する病気の総称で、かつては「成人病」と呼ばれていました。
代表的な生活習慣病には、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)、高血圧症、肥満症、心疾患(心筋梗塞・狭心症など)、脳血管障害(脳梗塞・脳出血)や、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、アルコール性肝障害などがあります。
みなさんも、こうした内容はニュースや新聞などで一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
これらの病気は、初期の段階ではほとんど自覚症状がなく、気づかないうちに進行しているケースが非常に多いのが特徴です。
だからこそ、定期的な健康診断の受診が重要になるのです。
がんのリスクも、決して他人ごとではありません。
日本では、2人に1人が一生のうちにがんにかかり、4人に1人ががんで亡くなると言われています。
(※出典:政府広報オンライン) https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201402/1.html#fourthSection
さらに、男性の63.3%、女性の50.8%が、人生の中でがんと診断される可能性があるというデータも示されています。
(※出典:国立がん研究センター「がん情報サービス」2021年)https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html
こうした数字を見ると、「私は大丈夫」と思っている方でも、誰にでもがんになる可能性がある時代だということがよくわかります。
特にがんは、早期であればあるほど治療成績が良いことがわかっており、
そのためには、症状が出る前の段階で、健康診断によって気づけることが何より大切です。
健康診断を受けるメリット7選
 さくら
さくらでは、早速、健康診断を受けるメリットを見ていきましょう。
- 病気の早期発見・早期治療につながる:自覚症状がない段階で異変を見つけられるので、重症化を防ぐことができる。
- 生活習慣を見直すきっかけになる:食事・運動・睡眠・ストレス管理など、自分の生活を振り返るチャンスになる。
- 重大な病気の予兆に早く気づける:脳卒中や心筋梗塞など、命に関わる病気を早い段階で察知できる可能性。
- 保健指導や栄養士のサポートが受けられる:ダイエットや生活習慣の改善をプロがサポートしてくれる。
- 長期入院や高額治療のリスクを減らせる:結果的に、本人だけでなく家族の精神的・経済的負担も軽くなる。
- 社会的なメリットもある:みんなが健診を受けることで、医療費や保険料の抑制にもつながりる。
- がんの早期発見・早期治療が可能となる:早期発見ができれば、それだけ完治の可能性が高くなる。また治療に要する費用や時間などの負担も軽くなる。
これらのメリットにより、健康診断は単なる検査にとどまらず、包括的な健康管理のための重要な機会です。
特に生活習慣病やがんのような無症状期に進行する疾患の早期発見・予防に不可欠です。
【体験談】乳がん検診で要精密検査と言われた私の記録
病院勤務の私は、職場の健診を毎年受けています。
10年ほど前のある年、検診結果を見てハッとしました。
「乳がん検診結果欄に要精査」と書かれていたのです。
え?これって、要再検査ってこと…?
…まさか私が?
驚きと不安で頭の中が真っ白になったのを、今でもよく覚えています。
精密検査までの不安な日々
すぐに乳腺外科受診の予約をし、精密検査を受けました。
結果が出るまでの約2週間は、不安で落ち着かない日々でした。
「がんを否定できないので、外科生検をおすすめします」
※外科生検とは手術で腫瘍の一部または全部を切除して組織を採取し、詳しく検査することです。
そう告げられたときの、あの冷や汗が忘れられません。
当時は中学生と高校生の息子がいて、「なるべく早く結果を知って、治療を始めたい」と強く思っていました。
手術の日、涙をこらえながら
局所麻酔の手術で、比較的簡単なものでしたが…
「まさか自分が手術を受けるなんて」そう思うだけで不安が込み上げ、涙がこぼれました。
「もし、がんだったらどうしよう」
「子どもたち、まだ手がかかるのに…」
そんな想いが、頭をぐるぐる巡っていました。
結果は…がんではなかった
外来で結果を聞いたときの言葉は今でも覚えています。
「異型細胞ですが、がんではありません」
安心したと同時に、医師からこう言われました。
「今は大丈夫でも、40代以降はがんの発症率が上がります。これからも年1回は検査を受けましょう」
それ以来、一般健診とは別に、毎年必ず乳がん検診も受け続けています。
「50代女性の健康診断ポイント」更年期・婦人科検診のすすめ
50代を迎えると、生活習慣病だけでなく、「がん」のリスクも少しずつ高まっていきます。
特に女性では、子宮頸がんは40代後半にピークを迎え、乳がんは40代後半と70代前半にピークがあると言われています(※厚生労働省データより)。
また、男性では前立腺がんが高齢になるほど増加傾向にあるため、見逃せません。
会社や自治体の健診では、基本的な生活習慣病検査に加えて、年齢や性別に応じた「がん検診」も受けておくことが、これからの自分を守るためにとても大切です。
必要に応じて、肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん・前立腺がんなどの検査も、ぜひ積極的に検討してみてください。
私のリアル体験談②:子宮体がんの疑い、そして今も定期検診へ
2年ほど前のことです。
閉経から数年が経っていたにもかかわらず、不正出血が続き、婦人科を受診しました。
医師からは「閉経後の不正出血は、子宮体がんの可能性があるため、必ず検査が必要です。」と説明されました。
再び、胸の奥がざわつくような不安な日々が始まりました。
結果として、がんではありませんでしたが、年齢より子宮の内膜が厚く、半年に一度の定期検診は必須と言われました。
更年期の体調変化にも注意を
50代に入ると、ホルモンバランスの変化により、体調が大きく揺れやすくなります。
- ホットフラッシュ
- 不眠
- 気分の浮き沈み
- 腰痛・肩こり
など、症状は多岐にわたり、長期化することもあります。
安心して通える婦人科を持つということ


幸い、私の場合は女性の気持ちに寄り添ってくださる先生との出会いがあり、安心して通える婦人科が住まいの近くにあります。
主治医の先生が話してくださった印象的な言葉があります。
「50代からは、若い頃のように無理はできません。自分のからだのメンテナンスは必須ですよ。」
「定期的に検診を受けることが、自分を守ることになりますよ。」
この言葉をきっかけに、私は自己判断で薬やサプリメントを選ばず、定期的な受診で体の状態を把握し、無理せず健康を保つことを意識しています。
同じように不正出血で不安になった方がいたら、ぜひ迷わず婦人科を受診してみてくださいね。
気になることは、早めの相談が自分を守る第一歩になります。
「自分の体を後回しにしないために」私の体験から伝えたいこと
私の経験から強く感じるのは、「自分の体を後回しにしないこと」の大切さです。
年に一度の健診を欠かさず受けること。
そして、「なんとなくおかしいな」と思ったら、我慢せずに早めに受診すること。
また、更年期の時期に特有の不調があれば、それを「年齢のせい」と片付けずに、信頼できるかかりつけ医を見つけて定期的に通院することをおすすめします。
50代は、自分の体にきちんと耳を傾けてあげるタイミング。
自分の健康を守れるのは、他でもない自分自身です。
※がん罹患率などの統計は、厚生労働省が運営する「がん対策推進企業アクション」のページでも詳しく紹介されています。
気になる方は公式サイトも参考にしてみてください。
●出典:厚生労働省「がん対策推進企業アクション」公式サイトhttps://www.gankenshin50.mhlw.go.jp/cancer/trend.html
(掲載ページ名:「がんの動向」)


まとめ
自分を大切に、健康でいることは、親の介護にもつながります。
50代を迎えた私たちは、親の心配だけでなく、自分の体にも目を向ける必要があります。
元気でいることが、結果的に親の支えにもなる。
それが介護における「第一歩」かもしれません。
「自分が病気になってしまっては、介護どころではない」これは、実際に多くの患者さんから聞かれる声です。
通院や入院が必要になってしまえば、どんなに「親の介護をしてあげたい」と思っていても、その想いを実現することは難しくなります。
私が勤務する病院でも、「自分の体を後回しにしていたら、入院になってしまった」と悔やまれる方が多くいらっしゃいます。
実際に私も、不正出血が続いたことで婦人科を受診し、子宮体がんの可能性を指摘されたことがあります。
幸い大事には至りませんでしたが、「あの時放っておかなくて良かった」と心から思いました。
「今は大丈夫」でも、何か異変に気づいたとき、ちゃんと自分に向き合うことの大切さを実感しています。
どうか、年に一度の健診と、「いつもと違うかも?」と思った時の受診を、迷わず行ってください。
それは、あなたの未来を守ることだけでなく、大切な親の未来を支えることにもつながります。
自分も、親も、安心して暮らせるように…
共に、良い未来にしていきましょう。
次回予告
次回予告、「親の退院後はどうする?施設という選択肢を考えてみよう」
親の突然の入院…
そして退院後の生活に悩むご家族は少なくありません。
そんなとき、在宅だけでなく「施設入所」も視野に入れておくと、心に少しゆとりが生まれます。
次回は、施設見学のポイントや、資料請求の方法についてお伝えします。
「どんな選択が親にとってベストなのか?」を一緒に考えていきましょう。

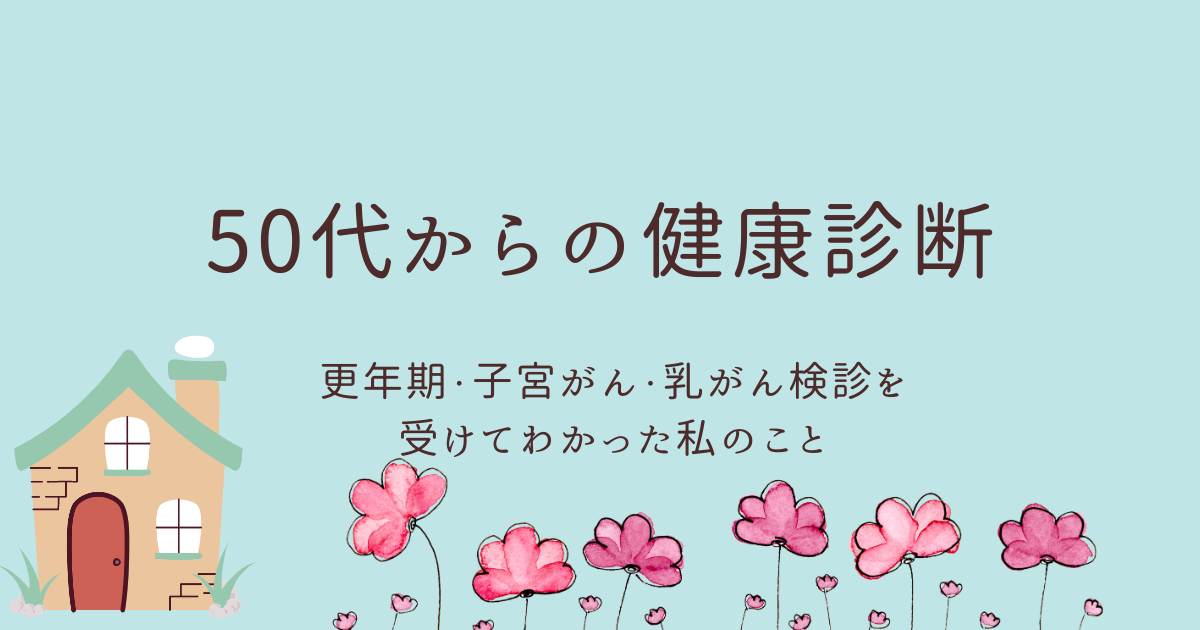
コメント