忙しい毎日のなかで、親御さんの介護は突然始まることがあります。
「布団の上げ下ろしがつらい」「段差でつまずきそう」
そんな日常の小さな困りごとから、介護の現実は始まっていきます。
こうした時に支えになるのが、介護保険を活用できるサービス です。
制度を知っていれば、必要な用具を費用を抑えてレンタル・購入できたり、自宅を安全に過ごせるよう住宅改修を行うことも可能になります。
前回の記事では、地域の中で支え合う 「地域密着型サービス」 について解説しました。
今回はその続きとして、
- 福祉用具貸与(レンタル)
- 特定福祉用具販売
- 住宅改修サービス
について整理し、実際の利用方法や選び方をわかりやすくお伝えします。

私は30年以上、急性期病院で看護師として働き、今は入院・退院支援や在宅生活のサポートにも関わっています。
現場で得た経験をもとに、介護保険サービスの実際を具体的に解説します。
これらを知ることで、親御さんが安心して暮らせる環境を整えることができます。
また、家族の介護負担を減らし、あなた自身の生活との両立にもつながります。
みなさんの不安がやわらぎ、親御さんの介護が安心して始められますように。
そんな願いを込めて、お届けします。
介護保険で利用できる介護用品(福祉用具サービス)
介護保険には、親御さんが住み慣れたおうちで安全・快適に過ごせるように支援する「福祉用具サービス」があります。
「福祉用具」とは、たとえば車いすや介護ベッド、手すりなど介護を助けてくれる道具のこと。
これらを利用することで、ご本人の生活が楽になるだけでなく、ご家族の介護の負担も軽くなります。
福祉用具は、すべてを購入する必要はありません。
介護保険を使ってレンタルしたり、一部は購入という形で利用できます。
費用の自己負担は、原則1割(所得によっては2割または3割)。
負担を抑えながら、必要な道具をそろえることができます。
介護保険で借りられる福祉用具(福祉用具の貸与)
 さくら
さくら「何が借りられるの?」と気になりますよね。
実は、対象になっている福祉用具は13品目と決まっていて、大きく2つのグループに分けられます。順番に説明していきますね。
要支援の方から利用できるもの(要支援〜要介護5)
- 手すり(工事不要で置くだけのタイプ)
- 歩行器
- 歩行補助杖
- スロープ(段差を解消する置き型の板)
- 自動排泄処理装置(※尿のみ対応)
要介護2以上の方が利用できるもの(要介護2〜要介護5)
- 特殊寝台(介護用ベッド)
- 寝台付属品(マットやサイドレールなど)
- 車いす(自走式・電動式・介助用など)
- 車いす付属品(座面クッションなど)
- 床ずれ防止用具(エアマットなど)
- 体位変換器(寝返りをサポートする道具)
- 移動用リフト
- 認知症老人徘徊感知機器
どうやって借りるの?福祉用具レンタルの手続き手順



「レンタルサービスを利用したいけど、手続き方法は?」と気になりますよね。
引き続き、わかりやすく説明していきます。
相談する
ケアマネジャーさんが、必要な介護用品を含めたケアプラン(介護サービス計画)を作ってくれます。
事業者・商品選び
ケアマネジャーさんが福祉用具貸与事業者(レンタル業者)を紹介してくれます。
福祉用具専門相談員が自宅を訪問し、体の状態や生活環境に合った用品を提案してくれます。
試用・納品
実際に使う前に、お試し(デモ品)を貸してくれる場合もあります。
商品が決まったら、事業者が自宅に届けて設置や使い方の説明をしてくれます。
契約・レンタル開始
利用する用品が決まったら、事業者と契約します。
契約後、レンタルがスタートします。
利用中のサポートについて
定期的に専門相談員が点検やメンテナンスに来てくれます。
必要があれば用品の変更もできます。
レンタルのメリット
- 購入より経済的
- 体の状態に合わせて交換可能
- 定期的にメンテナンスしてくれるので安心
- 必要がなくなったら返品できる
●「親の介護が始まったけど、何を用意すればいいの?」
そんな時、このレンタル制度を知っておくと心強いですね!
👉厚生労働省 介護事情所・生活関連情報検索
(公表されている介護サービス**福祉用具貸与**についての最新情報はこちらから確認できます。)https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group21.html
介護保険で利用できる購入サービス(特定福祉用具販売)



「購入サービスってなにが買えるの?」
「レンタルと購入、どっちが正解?」
そんな疑問をお持ちの方も多いと思います。
さっそく詳しくお伝えしていきますね。
購入サービス(特定福祉用具販売)とは?
このサービスは、特定の福祉用具を購入する際に、介護保険から補助を受けられる制度です。
たとえば「他の人が使ったものはちょっと…。」というような、肌に触れる個人使用のものや消耗品に近いものなどを対象に、市から費用の一部が補助されるイメージです。
補助内容の概要
- 年間上限:10万円までが対象(要介護度に関係なく一律)
- 自己負担:原則1割(所得に応じて2~3割)
- 支払い方法:いったん全額を立て替えて支払い、後日給付される「償還払い」
●購入先は「特定福祉用具販売事業者」に限られます。
これ以外から購入すると、介護保険が使えないので注意が必要です!
対象となる9品目(2024年現在)
- 腰掛便座(ポータブルトイレ・便座の高さ調節機能など)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品(尿・便が通るチューブなど)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽用手すりなど)
- 簡易浴槽(空気式・折りたたみ式など、工事不要のもの)
- 移動用リフトのつり具部分(肌に直接触れる部分)
- 排泄予測支援機器(排尿のタイミングを予測してお知らせしてくれる機器)
2024年4月からの変更点
※これまでレンタル対象だった「スロープ」「歩行補助杖」「歩行器の一部」が新たに購入対象に追加され、対象品目は【6品目 → 9品目】となりました。
👉厚生労働省 介護事情所・生活関連情報検索
(公表されている介護サービスについて**特定福祉用具販売**の最新情報はこちらから確認できます。)https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group22.html
レンタル?購入?迷ったときの選び方
| 視点 | レンタルがおすすめ | 購入がおすすめ |
|---|---|---|
| 使用期間 | 短期間・体の変化が見込まれるとき | 長期間使い続ける見込みがあるとき |
| 衛生面 | 気にならない場合 | 肌に触れるもの、衛生面が気になるもの |
| 費用面 | 高価な用具を試したいとき | 長期間でレンタル費がかさみそうなとき |
介護保険で利用できる住宅改修サービス



介護保険には、要支援・要介護の方が自宅で安全に生活を続けられるよう支援する「住宅改修サービス」があります。
ドアを引き戸に変更したり、手すりを設置するなど、小規模な工事が対象になります。
対象となる工事について
住宅改修の対象となるのは、次のような工事です。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消(スロープなど)
- 滑り防止や床材の変更
- 扉を引き戸への変更
- 和式便器から洋式便器への交換
- その他、これらに付随する小規模工事
いずれも「自宅で安心して暮らせる」ことを目的にしています。
費用面のこと
介護保険で利用できる住宅改修の上限は 20万円まで。
自己負担は所得に応じて1〜3割となります。
原則として「償還払い」という仕組みで支払われます。
これは、いったん利用者が工事費用を全額支払い、その後に市区町村へ申請し、保険適用分(7〜9割)が払い戻される方式です。
なお、20万円を超える工事費用は自己負担となります。
ただし、市区町村によっては独自の住宅改修助成制度を設けている場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
住宅改修サービス利用の流れ
自宅で安心して暮らすためには、ちょっとした住宅改修が役立ちます。
「手すりをつけたい」「段差をなくしたい」と思ったら、まずケアマネジャーに相談するところから始まります。
流れを知っておくと、いざ必要になったときに慌てずに進められます。
- ケアマネジャーに相談
日常生活で「ここが危ない」と感じる点を伝えましょう。
ケアマネジャーが必要性を確認し、「住宅改修が必要な理由書」を作成します。
- 施工業者を決めて見積もり依頼
業者はケアマネジャーから紹介してもらえる場合もあれば、自分で探すこともできます。信頼できる業者を選び、見積もりを取りましょう。
- 市区町村へ工事前申請
見積もりや理由書を添えて、市区町村に工事の申請を行います。
- 工事の実施
承認が下りたら、いよいよ工事スタートです。
- 工事費用を全額支払い(償還払い)
まずは利用者がいったん工事費用を全額立て替えて支払います。ここが「償還払い」のポイントです。
- 工事後の申請
工事が終わったら、施工写真や領収書を添えて市区町村に報告します。
- 介護保険から費用が戻る(償還払い)
上限20万円の範囲内で、介護保険から自己負担分を差し引いた金額が後日戻ってきます。
住宅改修の流れは少し複雑に見えますが、ケアマネジャーがしっかりサポートしてくれるので安心です。
「知っている」ことで、必要なときに落ち着いて行動できます。
親御さんが安全に暮らせる環境を整え、家族の負担を減らすために、ぜひ早めに理解しておきましょう。
合わせて読みたい病院での事例紹介
先日、70代半ばの女性Aさんが、股関節の手術のため入院予定となり、病院へ手続きに来られました。
ご主人は80代。おふたりで暮らしていらっしゃいます。
ご主人には脳梗塞の既往があり、現在は片麻痺のため、Aさんの支援がなければ生活が難しい状況です。
Aさんの入院期間は、およそ2〜3週間と主治医から説明を受けておられました。
こうした場合、「自分が入院している間、夫の介護はどうしよう…。」という不安を感じる方も多いものです。
今回は、Aさんの普段のご主人への支援の様子から、ケアマネジャーさんが必要性を判断し、介護保険の申請を勧めてくださいました。
すでに申請と調査が行われ、「要支援2」の認定を受けていました。
その後、Aさんが退院後の生活に困らないように、ベッドレンタルの手続きもあらかじめ済ませていたため、退院後すぐに使用できる体制が整っていました。
また、ご主人の生活状況をふまえて、ケアマネジャーさんがショートステイの手続きも進めてくださったことで、Aさんも安心して入院できる体制が整いました。
※実は、ご夫婦そろって介護認定を受けている場合、おふたりとも同じケアマネジャーが担当することは非常に多いです。
体調や生活状況、介護における役割分担を1人の担当者が包括的に把握できるため、支援がスムーズになるメリットがあります。
このように、「もしものときに備える」ことの大切さを感じさせてくれる実例ですね。
あなたとご家族が、これからも安心して過ごしていけるように。
一緒に少しずつ、準備していきましょう。


今日のまとめ
介護生活を安心して続けるためには、介護保険制度を活用した「福祉用具の貸与・販売」と「住宅改修」を知り、上手に利用することがとても大切です。
必要な用具や住環境を整えることで、介護する人・される人双方の負担を軽減し、安全で快適な暮らしを実現できるからです。
特に住宅改修は転倒防止や生活動線の改善につながり、在宅介護を支える大きな力となります。
たとえば、介護ベッドや手すりの貸与、ポータブルトイレの購入といった福祉用具に加え、段差解消や引き戸への変更といった住宅改修を組み合わせることで、日常生活の安全性がぐっと高まります。
さらに、制度を利用すれば自己負担を抑えて導入できるのも大きなメリットです。
制度を正しく理解し活用することが、親御さんの安心と快適さ、そして家族の介護負担軽減につながります。
この記事が少しでもあなたとご家族の支えになれば幸いです。
「居宅サービス」「地域密着型サービス」については、以下の記事で詳しく紹介しています。
よかったら参考にしてくださいね。
▶詳しくは【初心者でも安心!】介護サービスの種類と選び方①
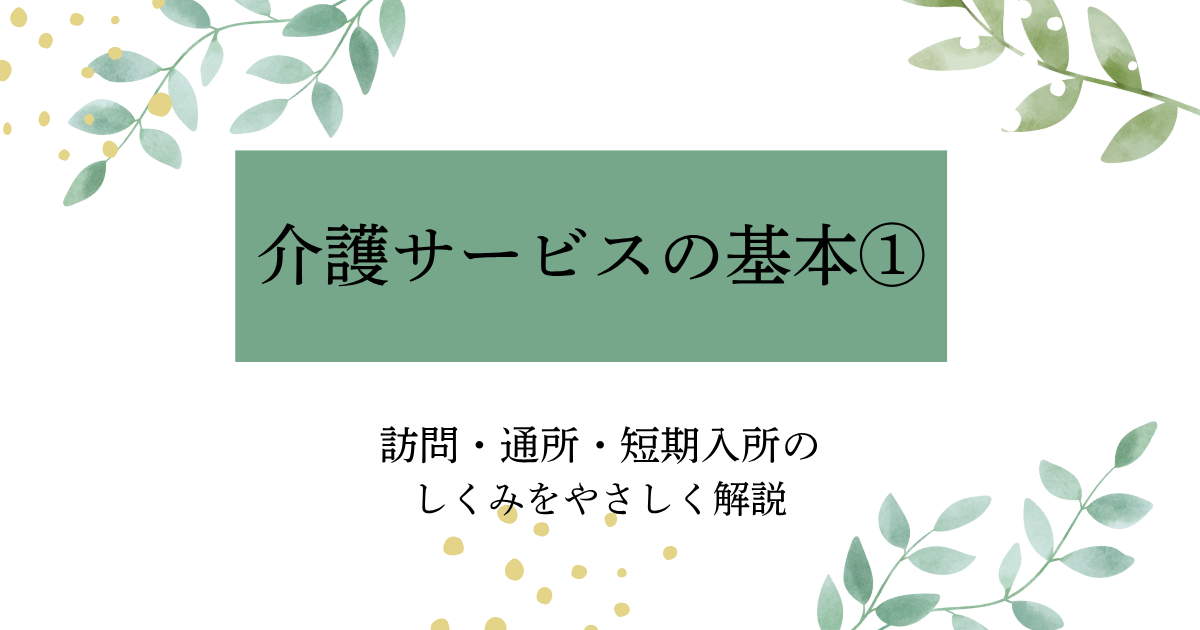
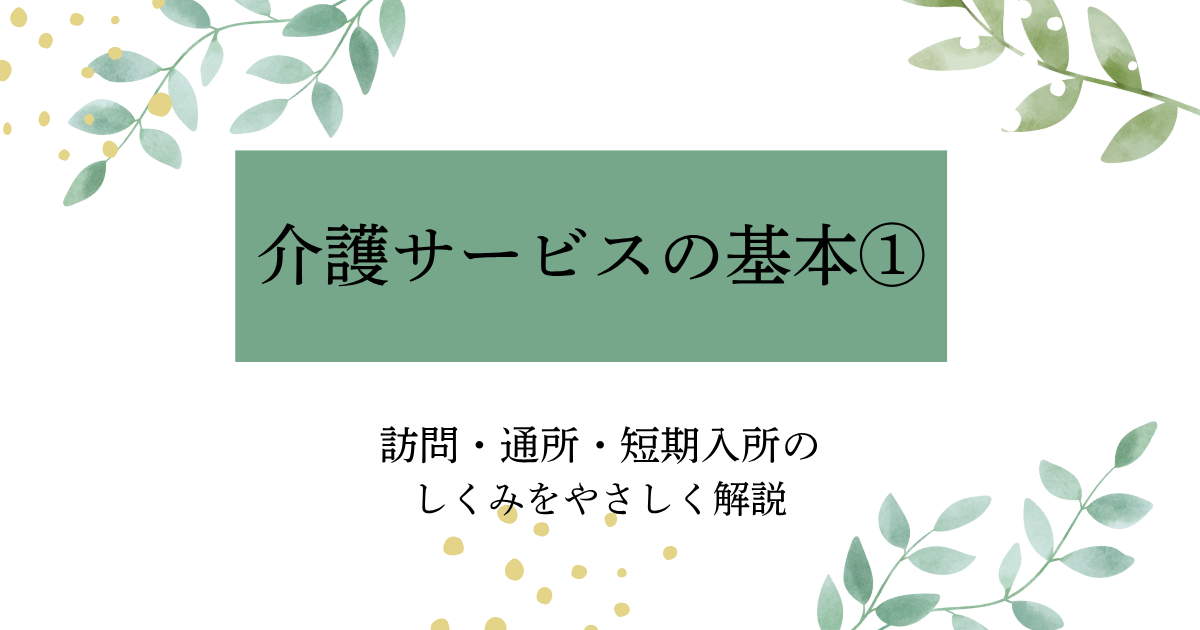
▶詳しくは【初心者でも安心!】介護サービスの種類と選び方②
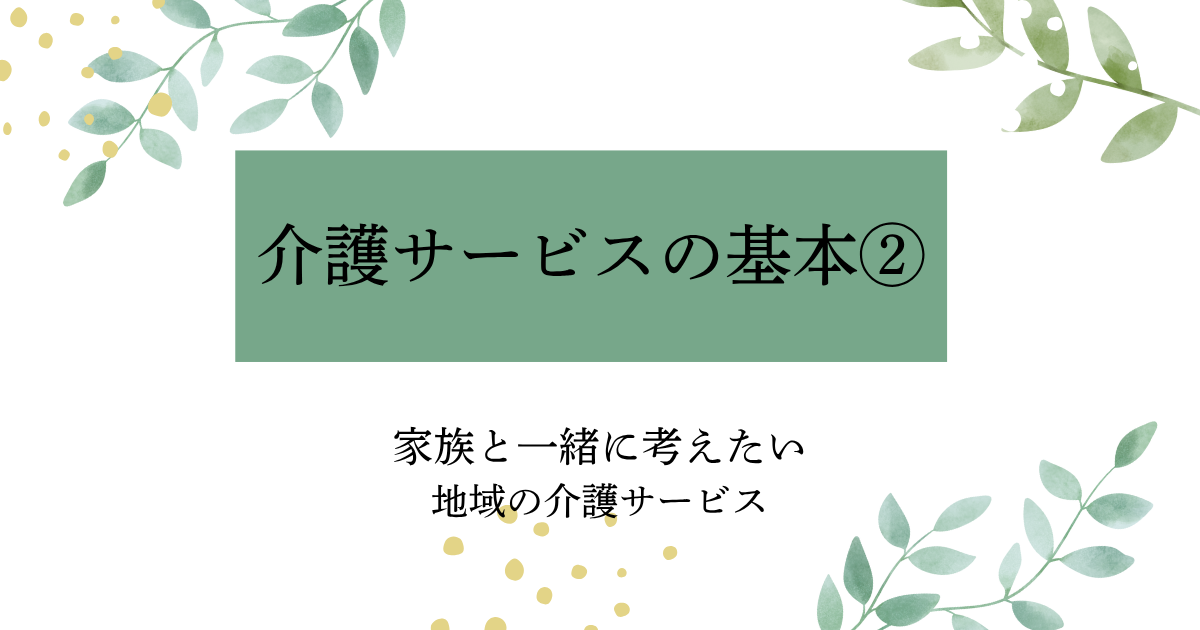
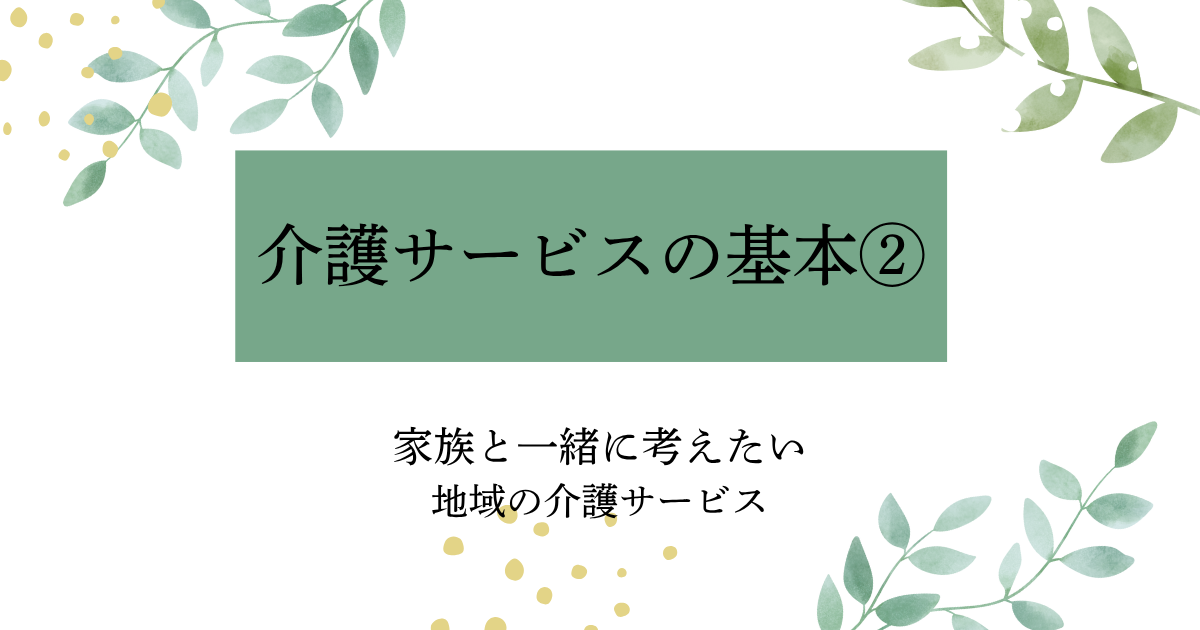
次回予告
●次回予告 ちょっとひと息、心がほっとする和菓子のお話です。
介護のお話は少しお休みして、次回は「親への贈り物」シリーズ。
実際に母がとても喜んだ贈り物をご紹介します。
ご両親へのプレゼントや、帰省時のお土産選びのヒントにしていただけたら嬉しいです。
どうぞ、楽しみにお待ちください。

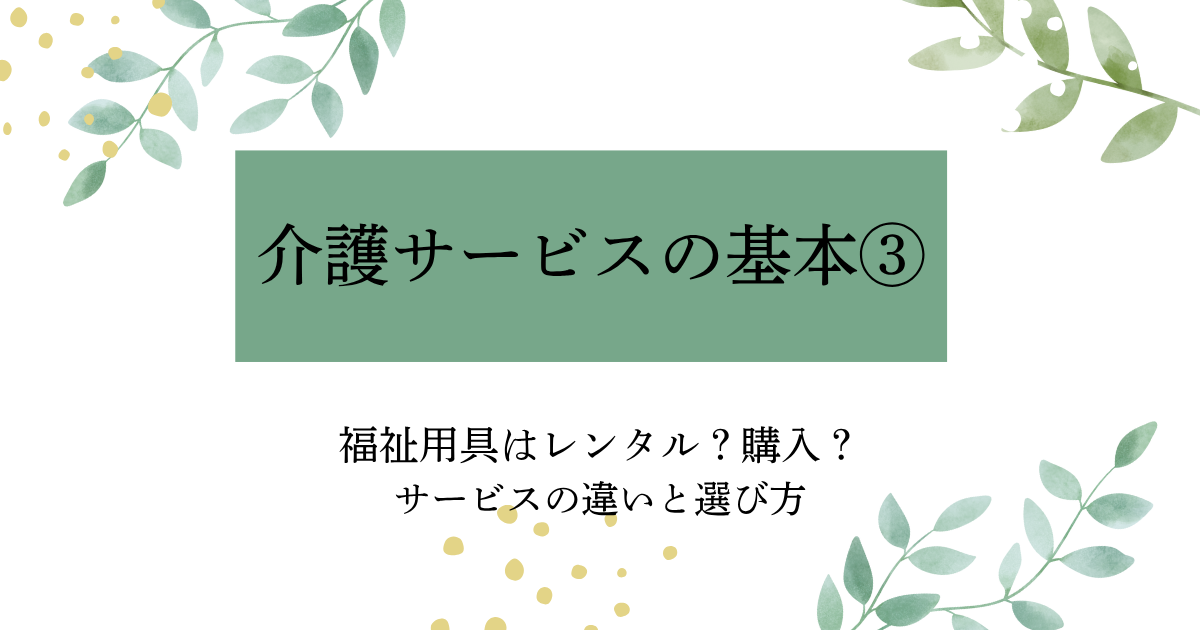
コメント