こんにちは。看護師として30年以上、医療と介護の現場に関わってきたさくらです。
親の老いと向き合いながら、50代の今を大切に暮らしています。
親の介護が必要になったとき、「どんなサービスを選べばいいの?」「そもそも何があるの?」と不安を感じたことはありませんか?
前回の記事では、在宅で受けられる「居宅サービス」についてわかりやすく解説しました。
今回はその続編として、「地域密着型サービス」の種類や特徴を紹介します。

地域で安心して暮らし続けるためには、地元の特性に合ったサービスを知っておくことが大切です。
この記事では、地域密着型サービスの特徴や違いを、現場経験をふまえてわかりやすく解説します。
今のうちから情報を知っておくことで、「親御さんに合ったサービス」を安心して選ぶことができるようになります。
「不安が軽くなった」「このサービスなら親にも合いそう」
そんなふうに思っていただけるよう、看護師としての視点から、実際に役立つ情報をお届けします。
いざという時にあわてずに済むよう、ぜひ最後までご覧ください。
地域密着型サービスとは?種類や特徴をわかりやすく解説
地域密着型サービスとは、「小規模多機能型居宅介護」や「地域密着型通所介護」など、住んでいる市区町村の住民が利用できる介護保険サービスのことです。
名前だけではわかりにくいと思うので、それぞれの特徴を以下でわかりやすく紹介していきますね。
できる限り顔なじみの人に囲まれ、家庭的な雰囲気の中で、安心して暮らし続けられるように支援する仕組みのひとつです。
住んでいる場所のすぐ近くにあり、原則として、その市区町村の住民しか使えません。
アットホームで、いつも同じ人が助けてくれることが多いのが特徴です。
認知症の人や、環境の変化に弱い人が、慣れない場所に行くと不安になったり、混乱したりすることがあります。
こういった理由で、住み慣れた地域の小さな施設でいつも同じスタッフに介護してもらうことで、安心して生活を続けられるような仕組みになっています。
地域密着型サービスの種類
 さくら
さくら「地域密着型サービスって、いろいろあるけど…正直、何がどう違うの?」
そんな方のために、今回はわかりやすく、やさしい言葉でご紹介していきますね。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
たとえば、「今すぐ来てほしい!」というときに、ヘルパーさんや看護師さんが、すぐに駆けつけてくれるサービスです。
決まった時間に来てもらう「定期巡回」と、困ったときに連絡して来てもらえる「随時対応」がセット。
「高齢の親が一人で暮らしで、急な体調変化が心配…。」というときの心強い味方です。
※要支援の方は使えません。
夜間対応型訪問介護
夜間に特化した訪問介護サービスです。
親御さんが夜間の時間帯に自宅で安心して生活できるよう、定期的に巡回訪問してくれます。
「夜中に具合が悪くなったらどうしよう…。」という不安、ありますよね。
このサービスがあると、ヘルパーさんがボタン一つで駆けつけてくれる安心感があります。
一人暮らしや、夜間に不安がある方におすすめです。
※こちらも要支援の方は対象外です。
地域密着型デイサービス(地域密着型通所介護)
近くの小さなデイサービスで、顔なじみのスタッフと一緒に過ごせます。
定員18名以下の小規模施設なので、利用者同士もすぐに打ち解けられる雰囲気です。
「大きな施設はちょっと苦手…。」という方にも、ぴったりですよ。
送迎サービスもあるので、安心です。
認知症対応型デイサービス(認知症対応型通所介護)
認知症と診断された方のための、専門的なデイサービス。
人数も12名以下で、とてもアットホームな環境です。
スタッフも認知症ケアに詳しいので、本人のペースを大切にしながら過ごせます。
「母が少し物忘れが…。」という方も、安心してご利用できます。
療養通所介護
難病の方や、医療的なケアが必要な方が利用するデイサービスです。
看護師が常駐しているので、医療的な処置や体調管理にも対応しています。
がんや難病などで、医療の支えが必要な方におすすめ。
小規模多機能型居宅介護
「今日は通って、明日は来てもらって、来週は泊まるかも。」
そんな風に、デイサービス・訪問介護・ショートステイを一つの事業所で柔軟に組み合わせて使えるのが魅力です。
ひとりひとりの生活スタイルに合わせて、使い方を自由に選べるのがうれしいポイント。
※ここのケアマネさんが担当になるため、他の事業所は使えません。
看護小規模多機能型居宅介護
上の「小規模多機能型居宅介護」に看護が加わったサービスです。
通い・訪問・泊まりに加えて、看護師さんによる医療的なケアも受けられます。
介護と医療の両方が必要な方には、ぴったりのサポート体制です。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方が、家庭のような雰囲気の中で共同生活を送る場所です。
1ユニットは5〜9人ほどの少人数。
スタッフの支えを受けながらも、自分らしく生活できる環境が整っています。
「できることは自分でしながら、見守ってもらいたい」という方に。
合わせて読みたい病院でのできごと
70代半ばの女性Sさんが、妹さんと2人で入院の手続に来られました。
今回はお薬の調整で、数日間の入院予定でした。
今年の冬、急激な腎臓機能低下により緊急で救急搬送されました。
入院時はほぼ寝たきり状態で、「死を覚悟した」とおっしゃていました。
2ヶ月の入院経過を経て、一旦退院されました。
もともとお元気で独居、近くに妹さんご家族が住んでおられました。
急な状態変化に、妹さんも驚かれた様子でした。
入院時点では介護サービスのご利用はなく、初めての申請手続きとなりました。
ご本人に代わり、70代の妹さんがあちこち走り回り手続をしてくれたそうです。
退院してからのサービス利用は下記です。
- 福祉用具レンタル:ベッド・ベッドサイドテーブル・玄関やトイレの手すり
- 訪問看護:週に1回 主に本人の体調の確認や内服の管理
- 通所リハビリ:週に1回(送迎付き)
- 配食サービス:毎日2食を配達(ご本人のご病気に合うよう腎臓食)
退院時は歩行もままならない状態でしたが、介護サービスのおかげでゆっくり、本人のペースで歩行できてお元気な様子でした。
今後も通院は続きますが、手厚い介護サービスのおかげで安心して暮らせているようです。
回復に伴い、要介護度も軽くなっていきますが、担当ケアマネジャーさんから「ご本人と相談しながら、最適なケアプランを提供していきます」と心強いお言葉をいただきました。
病院スタッフとしては、患者さんが安心して生活できているという想いで、感謝の気持ちがあふれる一日でした。
※ここで紹介している「配食サービス」は、介護保険の対象外のサービスです。
要介護の方が利用する場合は「生活援助型配食サービス」と呼ばれ、一般的には自費での利用になります。詳しく知りたい方は、私がまとめたこちらの記事も参考にしてください。
「居宅サービス」については以下の記事で詳しく紹介しています。
▶詳しくは「初心者でも安心!」介護サービスの種類と選び方①
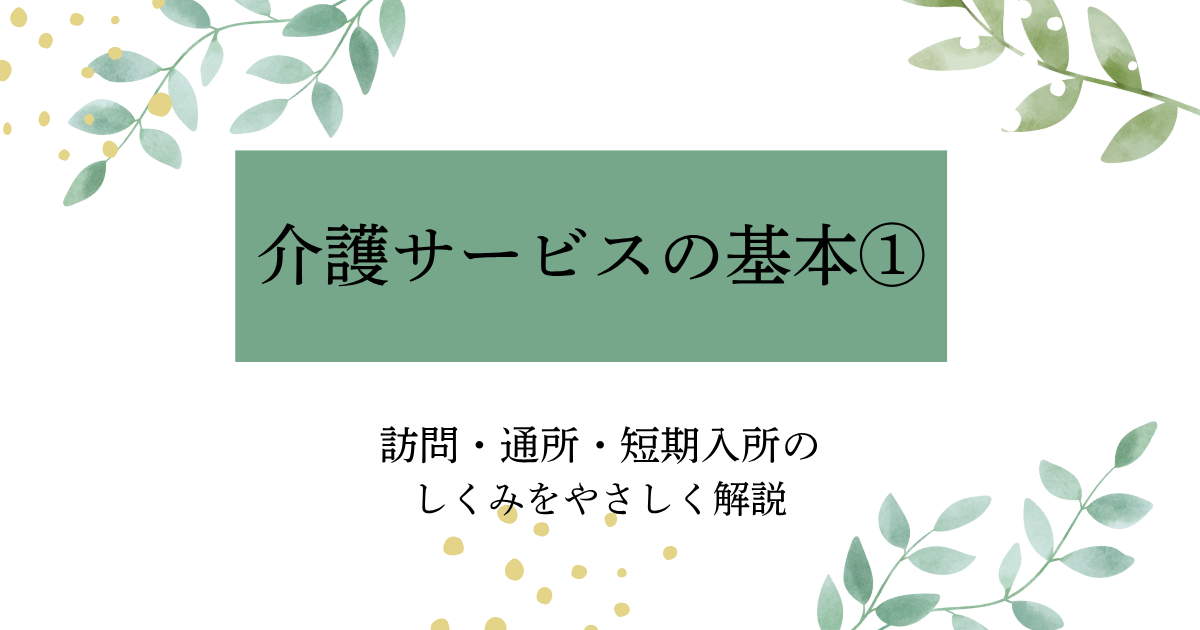
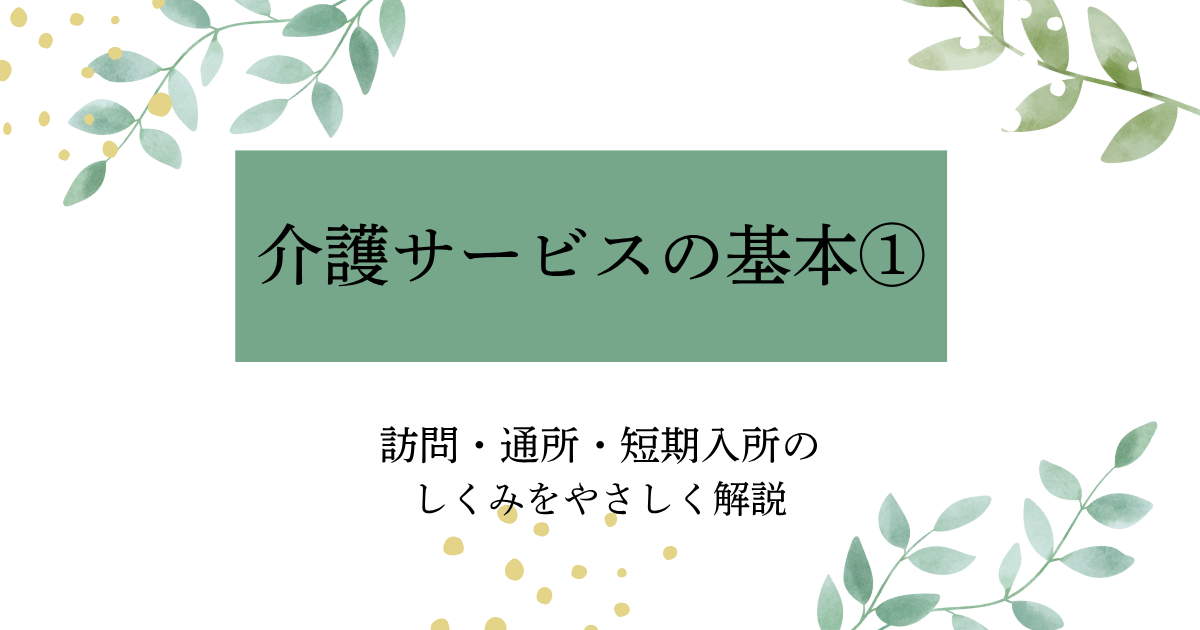
厚生労働省 介護事情所・生活関連情報検索
(公表されている介護サービスについての最新情報はこちらから確認できます。)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/


まとめ
「地域密着型サービス」は、親御さんの安心な暮らしを支えるために、早めに知っておきたい大切な介護サービスです。
「地域密着型サービス」は、住み慣れた地域で安心して利用できる仕組みです。
その地域の住民だけが対象となるため、より身近で、きめ細やかな支援を受けられる特徴があります。
たとえば、近所にある小規模なデイサービスや、夜間にも対応してくれる訪問介護などは、顔なじみのスタッフが対応してくれることで、ご本人にもご家族にも安心感が生まれます。
サービスの種類を知っておくことで、親御さんに合った選択肢が見つかり、家族の負担も軽くなります。
いざという時に慌てないためにも、「地域密着型サービス」について、今のうちに理解を深めておきましょう。
次回予告
●次回は「初心者でも安心!」介護サービスの種類と選び方③
「介護保険で利用できる介護用品」について、わかりやすくお届けします。
ぜひ、読みに来てくださいね。

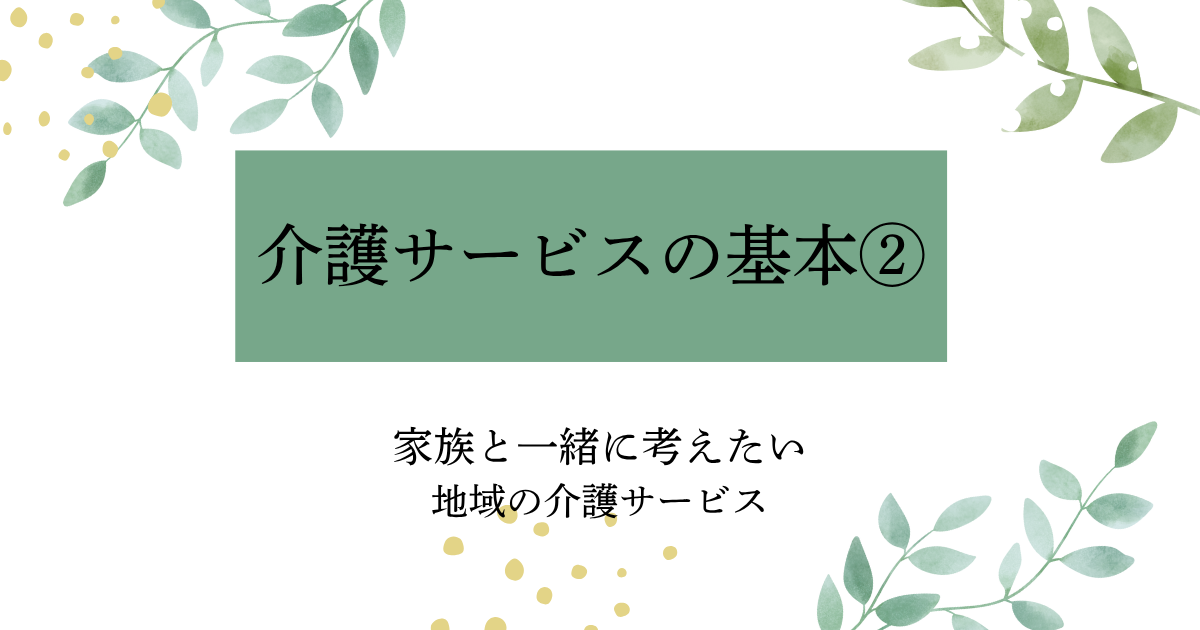
コメント